高齢期の住まいとして増える有料老人ホームと相続の関係
有料老人ホームは老人福祉法29条と改正高齢者住まい法に基づき都道府県へ届出を行う高齢者向け住宅です。
自立型から介護付きまで幅広いサービスが用意され、安心して老後を過ごせる住まいとして利用が拡大しています。
一方で入居後に相続が発生すると、入居一時金の返還請求や利用契約の解除、人件費や医療費の精算など多岐にわたる手続きがのしかかります。
厚生労働省の「有料老人ホームガイドライン」は一時金保全措置と分別管理を義務付けていますが、契約条項の理解不足がトラブルの火種になりやすいため、入居前から相続対策を並行しておくことが欠かせません。
有料老人ホームの仕組みと契約の特徴
ホームの種類とサービス概要
住宅型は生活支援サービスが中心で、介護サービスは外部の訪問介護事業所と個別契約になります。
介護付きは介護保険指定を受け、ホームが直接介護サービスを提供します。
健康型は自立者専用で、要介護認定を受けると退去または転居が必要です。
入居契約と重要事項説明
入居時には利用契約書と重要事項説明書を確認します。
国土交通省と厚労省の合同通知では、退去条件、原状回復義務、入居一時金の返還条項、短期解約特例(90日以内退去で全額返還)を明示するよう求められています。
入居一時金は平均三十六〜六十か月で均等償却され、死亡退去でも未償却残額が返還対象です。
身元保証人と預り金の管理
多くのホームが身元保証人を求め、利用料や医療費、遺体搬送費まで連帯保証させる契約となっています。
保証範囲を確認し、家族で対応が難しい場合は保証会社や専門NPOの利用を検討すると安心です。
預り金は法人運転資金と分別した口座で管理し、死亡後三十日以内の精算が望ましいとされています。
相続発生時に確認すべきこと
ホームへの連絡と契約終了手続き
入居者が亡くなったら速やかに施設へ連絡し、退去期限と残存利用料を確認します。
利用料は亡くなった日の翌日以降日割り精算となり、原状回復費が請求されるかどうかも契約条項で判断します。
入居一時金・保証金の返還請求
償却期間中に死亡退去した場合、未償却残額は相続人へ返還されます。
請求には戸籍謄本や遺産分割協議書が必要で、協議未了なら代表相続人による仮受領も可能です。
返還金は相続財産に含まれるため、相続税申告の対象になる点に注意が必要です。
家財の撤去と個人情報の取扱い
退去期限までに家財を撤去し、介護記録や医療情報の写しを取得しておくと、相続税・医療費控除の証拠資料として役立ちます。
施設によっては期限を過ぎると遺品を処分する場合があるため早めの対応が重要です。
相続準備としての実務対応
財産棚卸しと目録の共有
自宅不動産を売却済みの場合、相続財産は預貯金・証券・保険が中心になります。
通帳や証券会社のID、保険証券を一覧表にまとめ、負債や保証債務も併記して家族と共有しておくことで、相続人が短期間で全体像を把握できます。
公正証書遺言の活用
自筆証書遺言は保管と検認がネックになるため、公証役場で作成する公正証書遺言が推奨されます。
行政書士は文案整理と証人手配を行い、財産の帰属先や一時金返還金の分配方法を遺言に明記してトラブルを防ぎます。
医療同意と ACP の記録
入居契約書には終末期の医療方針欄があります。
延命治療の希望を家族会議(ACP)で共有し、エンディングノートに転記しておくことで、危篤時の医療同意トラブルを避けられます。
行政書士が提供できる支援
相続財産調査と目録作成
銀行照会状の作成、保険会社への請求書類、登記事項証明書の取得を代行し、正確な財産目録を作成します。
遺言書の作成・見直し
既存遺言のリーガルチェック、新規公正証書遺言の起案、公証役場日程調整まで一括サポートします。
遺産分割協議書と契約解約書類の作成
相続人全員の合意形成を助け、金融機関やホームへの提出書類を整備します。
弁護士・税理士・司法書士との専門家連携もスムーズに行えます。
まとめ:有料老人ホーム入居は相続対策の好機
有料老人ホームへの入居は生活の安心を得ると同時に、相続準備を始める絶好のタイミングです。
- 入居契約書と重要事項説明書を家族で共有する
- 財産目録と公正証書遺言を早期に整備する
- 一時金返還や医療費精算の条項を確認し、相続人が円滑に手続きできる体制を作る
行政書士と連携すれば、契約確認から遺言作成、相続発生後の協議書作成まで一貫してサポートを受けられます。
行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報(姫路市対応)
当事務所では有料老人ホームに関する契約確認、財産目録作成、遺言・家族信託・成年後見の導入支援、相続手続きまでトータルで対応しています。初回相談は無料です。
相続や介護に不安を感じたら下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、具体的な案件は行政書士または関係専門家へ直接ご相談ください。
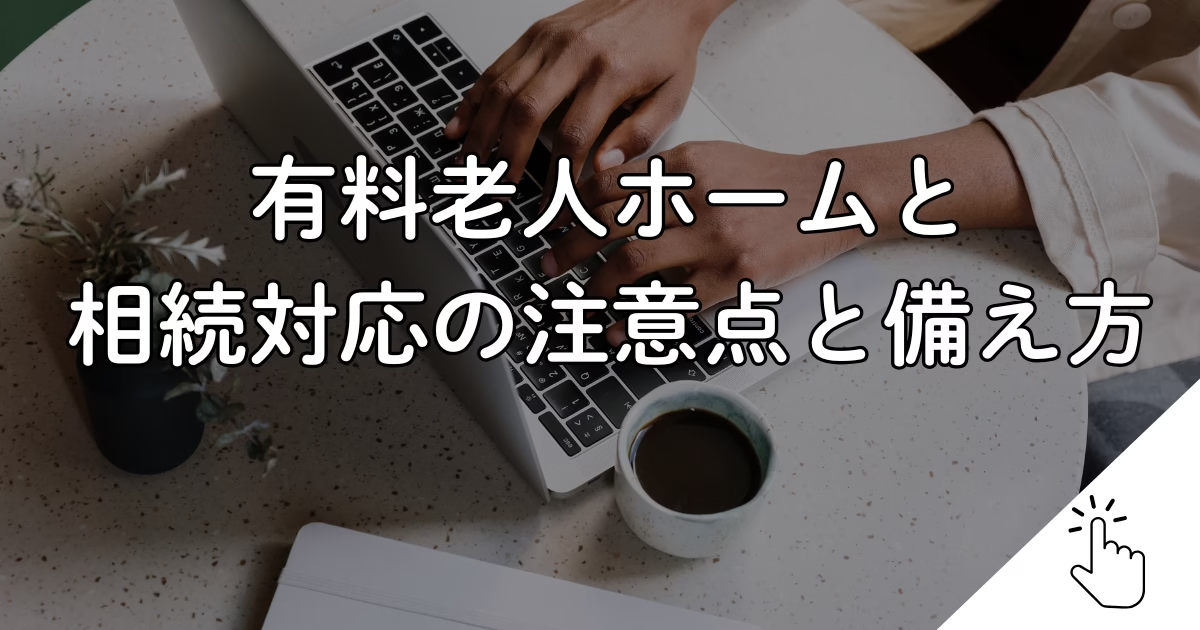
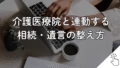
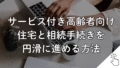
コメント