はじめに
「遺言を書いても、すぐに見つかる場所でも不安だし、万が一の時に見つけてもらえないのも困る…」
このように漠然とした不安を抱えていませんか?
相続対策の第一歩として、自筆証書遺言を作成することが重要です。しかし、遺言書の紛失や改ざん、無効になるリスクがあることを知っている方は少なくありません。
そこで、2020年7月10日にスタートした「自筆証書遺言保管制度」が注目されています。本記事では、この制度の3つのメリットについて詳しく解説します。
1. 遺言書を安全に保管できる
通常、自筆証書遺言は自宅などに保管することが一般的ですが、以下のようなリスクがあります。
- 紛失するリスク:どこに保管したのか分からなくなることがある
- 改ざん・偽造のリスク:意図しない内容に書き換えられる可能性
- 破棄されるリスク:相続人に不利な内容が含まれていると、意図的に破棄されることも
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を安全に保管してくれるため、こうしたリスクを回避できます。さらに、保管時に形式不備がないかチェックしてもらえるため、せっかく書いた遺言書が無効になる可能性を減らせるのも大きなメリットです。
しかも、公正証書遺言に比べ大変安価に利用することができます。1通につき3,900円で預かってくれ、万が一の際最大3名に遺言書が保管されていることを通知してくれます。
遺言書が見つからなかった、そもそも存在していることを知らなかったということを防ぐことができますね。
遺言書を預かってくれて、サンキュー(3,900円)と覚えておきましょう。
2. 検認が不要でスムーズな相続手続きが可能
通常の自筆証書遺言は、相続が発生した後に家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認とは、遺言書が偽造や改ざんされていないかを確認するための手続きで、相続人全員に通知が送られます。この手続きには時間がかかることが多く、相続人にとって負担となります。
それに遺産整理をしているときに遺言書が出てきたら、早速開封してみたくなるものです。
知らずに開封してしまった場合、民法1005条に基づき、5万円以下の過料が科される可能性があります。
民法第1005条(遺言書の検認)
家庭裁判所は、相続人、受遺者、その他の利害関係人の請求により、または職権で、遺言書を検認しなければならない。
2. 遺言書の保管者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
3. 遺言書を発見した者も、同様とする。
4. 前二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
さらに、検認を経ていない遺言書は改ざん、偽造の疑念がぬぐえないなど、正式な効力をもっていないとして相続手続きに影響を与える恐れがあります。
しかし、法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。つまり、相続開始後にスムーズに遺言の内容を実行することができ、相続人の手続きの負担を軽減することができます。
3. いつでも書き換えが可能で柔軟に対応できる
「遺言書を書いたけれど、途中で内容を変更したくなったらどうすればいいの?」
そんな不安を感じる方も多いかもしれません。
自筆証書遺言は、いつでも書き換えることが可能です。特に法務局に保管された遺言書は、新しい遺言書を作成し、古いものを撤回することが簡単にできます。
相続人の状況や財産の変化に応じて、柔軟に対応できるため、一度書いたら終わりではなく、ライフステージに合わせた相続対策が可能です。
ですから以前の記事に書いたように、今すぐ遺言書を用意して、都度変更していくことが大切です。公正証書遺言のように費用がかからないことも魅力ですね。
自筆証書遺言保管制度のデメリットは必ず本人が出頭しなければならない、ということです。
大概の役所の手続きは委任状を発行して弁護士や行政書士に代行してもらうことができますが、これだけは本人が直接法務局までいかなければいけません。
体が不自由になってからでは外出も困難になるので、今すぐ行動することが大切ですね。
まとめ:今すぐ相続対策を始めましょう!
「まだ遺言書を書くのは早い」と考えていませんか?
しかし、遺言書を作成する前に万が一のことがあれば、自分の意思を法的に残すことはできません。
自筆証書遺言保管制度を活用すれば、安全に遺言書を管理し、スムーズな相続手続きを実現できます。
「自筆証書遺言保管制度の注意点」
しかし、自筆証書遺言保管制度では、遺言書が法律の形式要件を満たしているかはチェックしてくれますが、内容はチェックしてくれません。
自分の望み通り遺言が書けているか、ほかにもっとよい方策があるかはやはり専門家のアドバイスが必要でしょう。
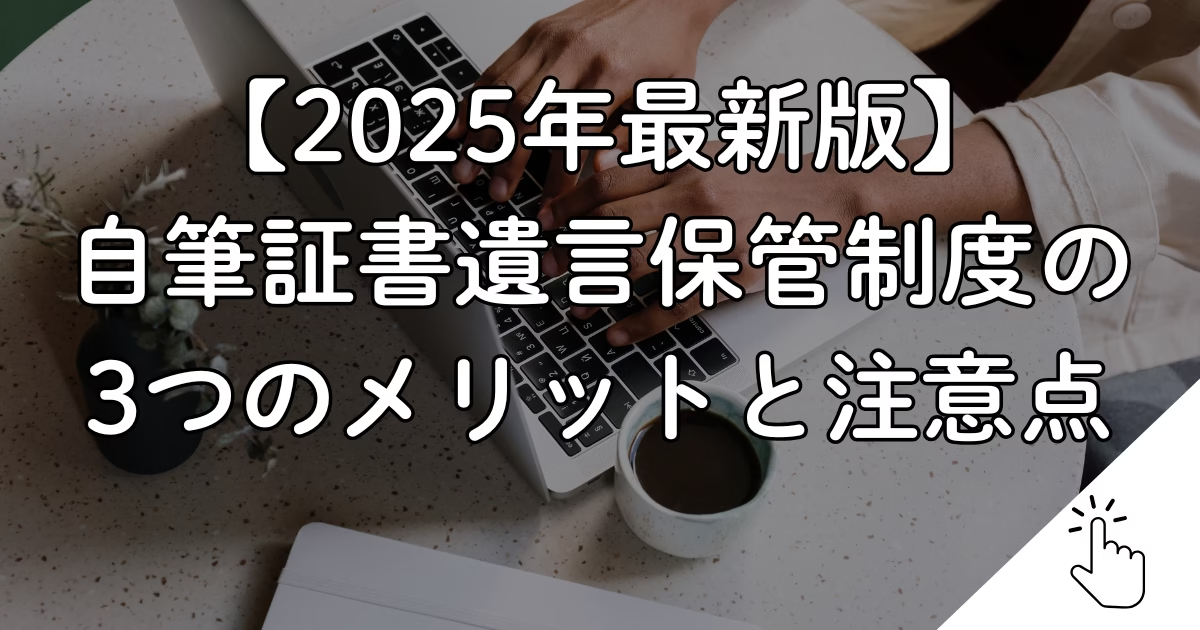
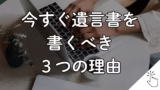
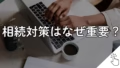

コメント