「相続のことは気になるけれど、まだ早いかもしれない…」、「難しそうだから、また時間があるときに…」とお考えではありませんか?
しかし、相続は突然やってくるものです。不幸にも万が一遺言書を作成しないまま亡くなってしまった場合、残された家族が困ることになりかねません。
本記事では、なぜ今すぐ遺言書を書くべきなのか、その理由を3つの視点から解説します。最後までお読みいただくことで、早めの相続対策の重要性を理解し、安心して対策を進めることができます。
1. 遺言書を残す前に万が一のことがあったら、遺言書以外の方法で残した自分の意思は法的に効力がない
「自分が亡くなった後、家族が自分の思いを汲んで財産を平等に分けてくれるだろう」と思っている方も多いですが、遺言書がなければ、遺産分割協議によって財産が分配されることになり、話し合いがまとまらないこともあります。
よくある思い違い
- 口頭で伝えていたから思いは伝わっているはずだ:言った言わないの水掛け論に発展しがち。たとえボイスレコーダーやビデオ動画などを残していたとしても、遺言書としての法的効力はありません。
- エンディングノートを残したから安心だ:遺言書の要件は民法で固く定められていて、1つでも要件が合致しないと法的効力を持ちません。したがってエンディングノートで詳細に自分の意思を残していたとしても、遺産分割協議の材料になることはあるかもしれませんが、それ自体法的効力はありません。
民法第968条(自筆証書遺言)
(第1項)
遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
(第2項)(※2019年改正)
遺言者は、遺言の内容の一部として財産目録を添付する場合、その目録については自書しなくてもよい。 ただし、その全ページに署名し、押印しなければならない。
このように民法では、遺言書の満たす要件について細かく定めていますので、それ以外の様式ではNG。
特に、不動産など分けにくい財産がある場合は、遺言書なしでは相続人間で意見が対立しやすく、最悪の場合、裁判に発展することも。
遺言書があれば、自分の意思を明確に示し、スムーズな相続を実現できます。
2. 遺言書はいつでも新しいものに書き換えることができるから
「まだ遺言書を書くには早い」、「また気が変わるかもしれないから、すべて確定してから書こう」と思っている方も多いですが、遺言書は一度作成したらもう二度と変更できないというわけではありません。
遺言書は何度でも変更可能
- 家族構成が変わった場合(結婚、離婚、子どもの誕生など)
- 財産の状況が変わった場合(新しい不動産の購入、事業の成功など)
- 相続人の関係性が変わった場合(仲違いや和解など)
- ただ気が変わった場合(つまりいつでも)
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、何度でも新しいものを作成でき、作成日付の一番新しい遺言書のみが法的に有効な状態を保つことができます。
「いつでも書き換えられるから、とりあえず今の時点で作っておこう」という気持ちで始めることが重要です。ただし、古い遺言書をいろいろな場所に残しておくと、後にどれが最新の遺言書かわからなくなりトラブルになるかもしれませんので、遺言書を再度作成したときは、古いものは処分しておきましょう。
3. 人間は難しい物事を後回しにしがちだから
相続の話は重く、考えるのを避けたくなるテーマです。まして自分が死んだときのことなんて考えただけでも気が滅入る、そう考えるのもよく理解できることです。そのため、多くの人が「まだ元気だから」、「また気が向いたときに…」と先延ばしにしてしまいます。
しかし、いざ相続が発生してからでは手遅れです。
後回しにすることのリスク
- 突然の病気や事故で遺言書を作成できなくなる
- 認知機能が低下した場合、遺言書を書くことができなくなる
実際に、遺言書がないことが原因で相続トラブルに発展するケースは少なくありません。
「いつかやろう」と思っているうちに時間は過ぎてしまいます。早めに遺言書を作成することで、家族の負担を減らし、円満な相続を実現しましょう。
まとめ:遺言書を作成して、家族に安心を
✅ 遺言書がないと、自分の意思が反映されず、家族が困る可能性がある
✅ 遺言書は何度でも変更できるので、今すぐ作成しても問題なし
✅ 後回しにすると、いざというときに作成できず、家族に負担をかけることに
「遺言書を書こうと思っていたけれど、何から始めればいいかわからない…」という方は、専門家に相談するのがベストです。
三好行政書士事務所では、相続対策の無料相談を実施しています。
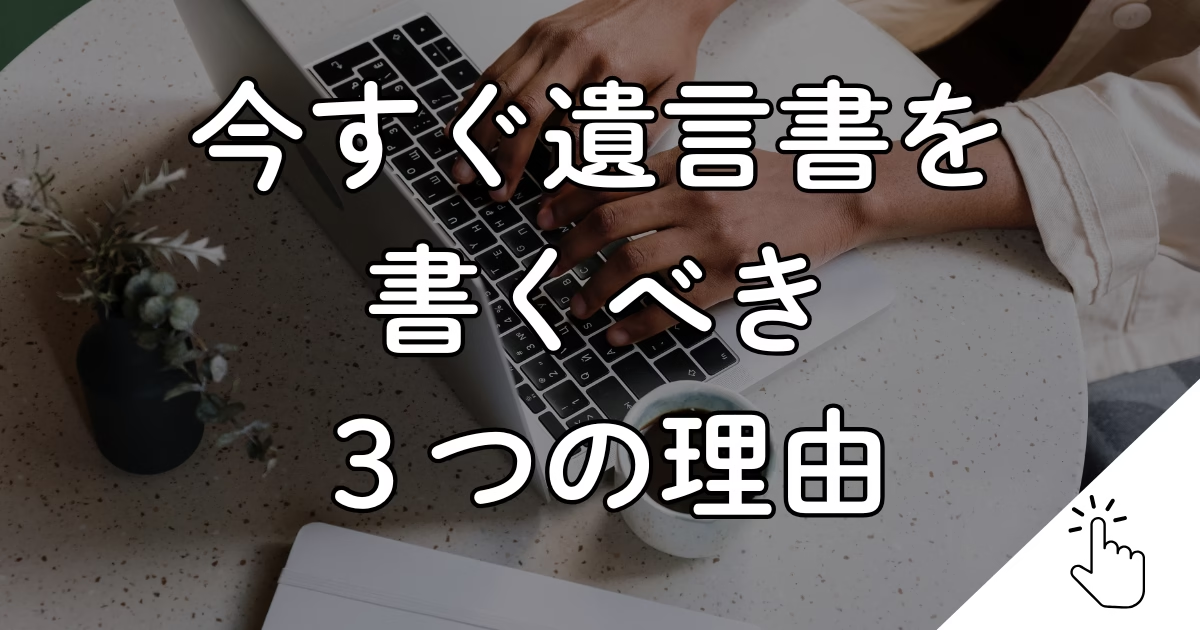
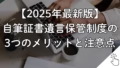
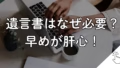
コメント