(この記事は一般的情報の提供を目的としており、個別事案については必ず専門家にご相談ください)
「まだ元気だから」「財産は少ないから」と遺言書を後回しにしていませんか?
遺言書を残さなかった結果、兄弟姉妹が絶縁、内縁配偶者が無権利、裁判沙汰に発展――。兵庫県姫路市で相続相談を受ける行政書士として、実際に見聞きした“10の対立シナリオ”と、法律・公的制度を踏まえた回避策を解説します。
遺言書を書かないと起こる10の対立シナリオとは?
1. 兄弟が口をきかなくなる—遺産分割協議の泥沼化
- 法的背景:相続人全員の合意が必要(民法906条)
- 実務ポイント:遺産評価や特別受益・寄与分の主張が紛糾しやすい
- 回避策:配分割合と理由を遺言で明示+付言事項で感謝を添える
2. 内縁配偶者が「赤の他人」扱い
- 法定相続権なし(民法890条)
- 救済策:遺贈/負担付遺贈、家族信託、生前贈与
3. 不動産共有で売れない・貸せない
- 共有持分の売却には原則全員同意(民法251条)
- 解決策:特定受遺引受人指定か、代償分割を遺言に盛り込む
4. 行方不明の相続人がいて手続き停止
- 失踪宣告や不在者財産管理人申立てが必要(家事事件手続法200条)
- 遺言書があれば:遺言執行者が単独で手続可(民法1012条)
5. 借金相続放棄を巡る混乱
- 相続放棄は自己のために相続の開始を知った時から3か月以内(民法915条)
- 遺言で負債承継先や保険金充当策を明記→判断材料を家族に残す
6. 予期せぬ借金で家族が連帯保証人に
- 信用情報の調査不足で負債判明が遅れる
- 対策:負債一覧を財産目録に記載+遺言書保管制度で安全管理
7. 「優遇された子ども疑惑」で遺留分請求
- 遺留分侵害額請求(民法1046条)で配分が修正される可能性
- 付言事項で生前贈与や介護負担の事情を説明→感情的軋轢を緩和
8. 介護した子が報われない
- 寄与分主張には裁判所の判断が必要(民法904条の2)
- 感謝遺贈+介護記録を証拠化→紛争コストを抑制
9. 認知症発症後の遺言が無効に
- 判断能力要件(民法963条)
- 早期作成+専門家関与+公正証書遺言で真正担保
10. 裁判沙汰で家族関係が修復不能
- 遺産分割調停→審判→訴訟の長期化
- 時間・費用・人間関係の三重損失を防ぐ“遺言書+家族会議”
遺言書作成で得られる3つのメリット
- 家族間の対立予防—法的根拠が明確
- 手続コスト削減—不動産名義変更もスムーズ
- 意思尊重の安心感—内縁配偶者・介護従事者の保護
行政書士が提供できるサポート
| サービス | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆・公正証書遺言作成支援 | ヒアリング→文案作成→チェック | 訴訟代理は弁護士紹介可 |
| 相続人関係図・財産目録作成 | 戸籍調査・登記事項証明書収集 | 電子データ納品可 |
| 遺言執行者就任 | 執行・名義変更・金融機関手続 | 行政書士法§1条の3適合業務 |
行政書士は「書類作成の専門家」です。裁判代理行為は弁護士が対応しますので、必要に応じ連携いたします。
よくある質問(FAQ構造化データ推奨)
Q. 公正証書遺言の費用は?
A. 遺産総額に比例し手数料が変動(例:1,000万円の場合1.1万円)。詳細は日本公証人連合会をご確認ください。
Q. 遺言書保管制度と公正証書、どちらが安全?
A. 紛失防止なら保管制度、真正担保なら公正証書。併用も可。
まとめ
遺言書は“書かないリスク”をゼロにする最短ルートです。
兄弟不和・生活破綻・裁判沙汰――この三重苦を未然に防ぐため、今日から準備を始めましょう。
今すぐできる第一歩
LINE公式から気軽にお問合せができます
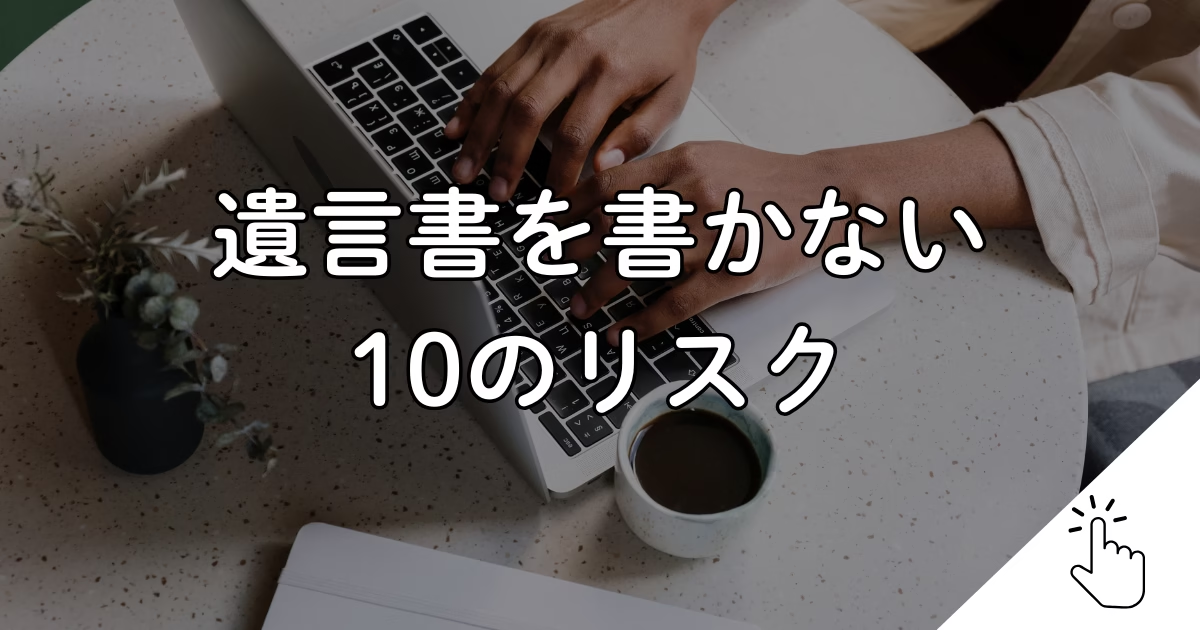
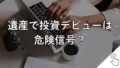
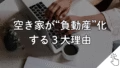
コメント