高齢化社会で注目される特養と相続の関係
厚生労働省統計では、要介護3 以上で在宅生活が難しい高齢者の約5 人に1 人が特別養護老人ホーム(以下「特養」)へ入所しています。
終のすみかとして暮らしの安心を得る一方、入所期間中や死亡後には特養 相続をめぐる相談が急増しています。
姫路市内でも行政書士へ寄せられる相談の三割近くが「預り金精算」「身元保証人の債務範囲」「自宅売却と遺言」の組み合わせです。
入所契約は老人福祉法20条と介護保険法8条の2に基づく施設サービス契約であり、財産管理や相続と密接に結び付いています。
特別養護老人ホームの特徴と入所条件
公的施設としての位置づけ
特養は社会福祉法人や地方自治体が運営し、要介護3 以上の高齢者に長期的な生活支援を提供します。
費用は「介護報酬+食費・居住費」で構成され、所得区分に応じて負担限度額認定証を取得すれば食費・居住費が軽減されます。
介護老人保健施設との違いは、別ブログ記事で解説していますので参考にしてください。
入所契約と身元保証人
多くの施設で連帯保証人または保証会社の選定を求められます。
保証義務は利用料や医療費、葬儀費、遺体搬送費まで及ぶ場合があり、契約書で債務範囲を必ず確認してください。
厚生労働省の「特別養護老人ホーム人権擁護指針」は過度な保証を避けるよう示しています。
自宅を離れると起きる財産管理の課題
空き家となった自宅は固定資産税や維持費が発生します。
空き家対策特別措置法14条により「特定空家」に認定されると行政代執行や固定資産税6倍課税の恐れがあります。
入所前に売却・賃貸・家族信託を検討し、将来の相続人間トラブルを防ぐ計画が不可欠です。
入所前から進める相続準備
財産の棚卸しと書類整理
預金、不動産、証券、年金、保険契約などを一覧表にまとめ、通帳コピーや登記簿謄本、保険証券を同封したファイルを作成します。
意思能力が低下しても代理人が迅速に把握できる体制になります。
公正証書遺言で思いを可視化
入所中は外出制限があるため、公証人が施設へ出向く「出張証人制度」を利用し公正証書遺言を作成すると安心です。
相続人が少ない場合も、預り金や自宅売却益の用途を明示しておくと争いを防げます。
行政書士は文案作成と証人手配でサポートします。
口座管理は家族信託・成年後見で安全運用
生活費や医療費を子が代理で支払うには、家族信託で受託者名義の信託口座を設定する方法が安全です。
判断能力が低下した場合は家庭裁判所に後見人を申し立て、後見人名義で金融取引を行います。
あらかじめ誰を後見人に指定するか決めておける、任意後見契約も検討することができます。
死亡後に必要となる特養関連手続き
施設への連絡と預り金精算
死亡届提出後、施設は翌日以降の利用料を日割り計算し、30日以内を目安に預り金を相続人へ返還します(厚労省「預り金ガイドライン」)。
遺品は原則7日で引き取りが求められるため、あらかじめ荷造りサービスを予約しておくと負担を軽減できます。
相続財産の確定と評価
施設利用中に費消された預金、売却済みの自宅代金、預り金返還額を含め財産目録を更新します。
相続税の課税対象かどうか国税庁の「財産評価基本通達」を照合し、必要なら税理士と連携してください。
遺産分割協議と公平性の確保
特養入所費が長期化すると、子どもが立替払した金額が大きくなりがちです。
領収書と振込控えをまとめ、立替金債権として協議書に計上すると公平感が保たれます。
行政書士が遺産分割協議書の作成と戸籍収集を一括で支援します。
行政書士が行う具体的サポート
財産目録と相続人調査
銀行照会状、残高証明書、戸籍謄本を収集し、負債や保証債務を含む目録を作成します。
空き家の固定資産税課税明細書も忘れずに取り寄せます。
遺言書作成・執行
公証役場との日程調整や証人同席、遺言執行者への就任で第三者として公平に手続きを進めます。
成年後見・家族信託コンサルティング
後見申立書式作成から家庭裁判所提出までを代行します。
信託契約書をドラフトし、信託口座開設の金融機関連絡を行います。
まとめ―特養入所は相続準備の好機
特別養護老人ホームへの入所は安心した老後生活を支える一方、財産管理と相続対策が欠かせません。
預り金精算や住所地特例、身元保証人の範囲といった法的ポイントを押さえ、公正証書遺言や家族信託で意思を可視化することで、家族の負担を大きく減らせます。
行政書士と早めに連携し、終活の質を高めていきましょう。
行政書士への相談窓口(姫路市対応)
当事務所では特養入所者とご家族を対象に、相続財産調査、遺言書・家族信託の作成、成年後見申立て、遺産分割協議書作成などを包括支援しています。
初回相談は無料ですので、特養、相続や預り金精算でお悩みの方は下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、具体的な案件は行政書士または関係専門家へ直接ご相談ください。
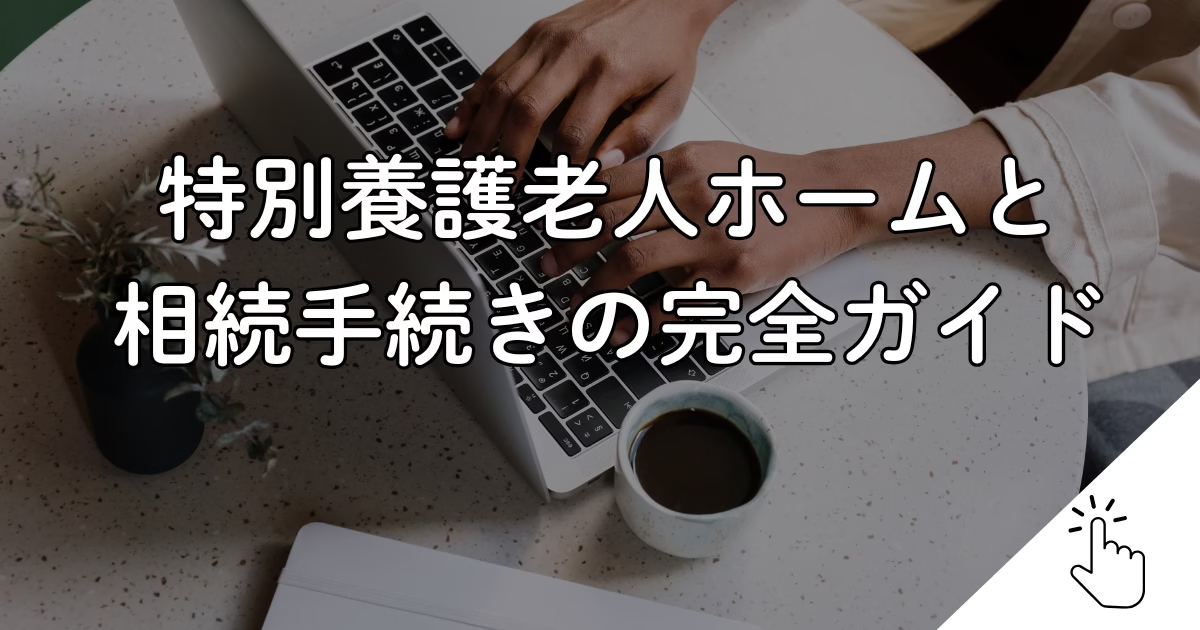
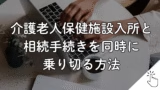
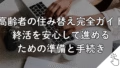
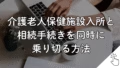
コメント