人生の最期を主体的にデザインする時代
医療技術の進歩によって延命措置は多様化し、治療の選択肢が広がりました。
一方で「治る見込みがない状態ならば、むやみに管につながれず、自分らしく旅立ちたい」と望む声も高まっています。
自己決定権(憲法十三条)を最期まで貫く手段として注目されるのが尊厳死宣言です。
特に公正証書で作成すれば、家族や医療機関に対して強いメッセージとして機能し、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」でも推奨されるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の一資料として活用できます。
本稿では行政書士の視点から、尊厳死宣言公正証書の意義、作成方法、法的限界、準備のコツをわかりやすく解説します。
尊厳死宣言とは何か
尊厳死とは、医学的に回復不可能な末期状態に陥ったとき、人工呼吸器や経管栄養、心肺蘇生などの延命治療をあえて行わず、自然経過に委ねて安らかな死を迎える考え方です。
医師が命を積極的に終わらせる安楽死とは異なり、治療を「しない」選択を意思表示する点に特徴があります。
尊厳死宣言はその意思を文書化したもので、医療現場ではリビングウイルとも呼ばれます。
公正証書による尊厳死宣言のメリット
尊厳死宣言には自筆証書や協会の様式、市販キットなど複数の形式がありますが、公正証書を推奨する理由は三つあります。
第一に、公証人が本人確認と自由意思を慎重に確認するため、後で「書かされたのでは」と疑われにくいこと。
第二に、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクがほぼないこと。
第三に、医療・介護現場での信頼度が高いことです。
公的第三者が関与しているという事実だけで治療方針決定時の指標になりやすく、家族内の感情的対立も緩和します。
公正証書作成の流れ
まず行政書士に相談し、本人の価値観や医療観をヒアリングして宣言文案を作成します。
延命治療の対象を人工呼吸器、経管栄養(経鼻胃管や胃ろうなど)、透析、輸血、心肺蘇生まで具体的に列挙し、「痛みや不安を和らげる緩和ケアは受ける」など希望内容を明確にします。
完成した文案を持参して公証人役場へ行きます。
公証人は本人確認書類と意思能力をチェックしたうえで内容を朗読し、自由意思であることを確認します。
証人二人(推定相続人や受遺者は除く)が立ち会い、公正証書が完成します。
手数料は通常一万円台、公証人との調整を行政書士に依頼した場合は別途報酬が加わります。
署名後の保管と周知
原本は公証役場に保管され、本人には正本と謄本が交付されます。
謄本を主治医に渡してカルテに添付してもらい、家族にもコピーを配布して所在を共有します。
スマートフォンの緊急医療情報にPDFを格納するなど、複数ルートで可視化しておくと救急搬送時にも意向が伝わりやすくなります。
尊厳死宣言の法的効力と限界
尊厳死宣言公正証書は法律上の強制力を持つわけではありませんが、医療契約の準委任関係において患者の自己決定権を示す最有力な証拠となり、医師はガイドラインに従い可能な限り尊重します。
ただし家族が強く延命を希望し、医療チームの判断も割れる状況では宣言がそのまま実行されないこともあります。
そのため作成後に家族と話し合いを重ねておくことが不可欠です。
また宣言は医療行為をするかしないかを示すもので、積極的に死期を早める行為は認められません。
行政書士が提供できるサポート
行政書士は本人の意思聴取を通じて宣言内容を文章化し、公証人との日程調整、証人手配、費用試算など手続きを一括で支援します。
必要に応じて家族会議の仲立ちをし、意思の共有を図る役割も担います。
任意後見契約や死後事務委任、遺言書作成、エンディングノート支援と組み合わせれば、終末期から死後事務まで抜け漏れなく備えることができます。
まとめ 尊厳死宣言は「生き切る」ための準備
尊厳死宣言は延命治療を拒む書類ではなく、最後まで自己決定権を行使し、「自分らしく生き切る」ことを支える道具です。
公正証書で残すことで信頼性が高まり、ACPの文書として医療・介護チームが共有しやすくなります。
行政書士の伴走支援を得て、一人ひとりが納得できる最期のデザインを早めに整備することをおすすめします。
行政書士への相談とサポート内容(姫路市対応)
姫路市の当行政書士事務所では、尊厳死宣言公正証書の文案作成、公証人との連携、証人手配、家族向け説明会の開催まで丁寧に支援しています。
初回相談は無料です。尊厳死宣言やACPに関心のある方はどうぞ下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、具体的な医療判断や法的対処は必ず医師・弁護士など専門家にご相談ください。
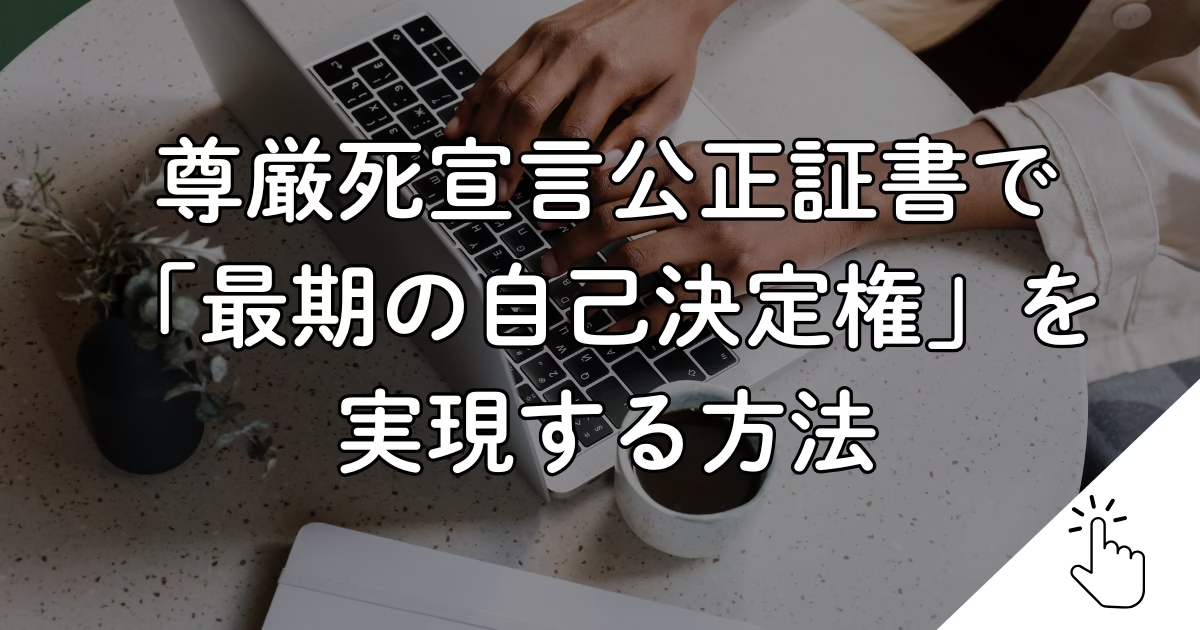

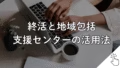
コメント