サ高住入居と相続が交差する現実
サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)は、改正高齢者住まい法に基づき都道府県へ登録された「バリアフリー賃貸住宅」です。
安否確認・生活相談などのサービスが付帯し、要介護度にかかわらず自由度の高い暮らしを実現できます。
ただし入居者が亡くなると、賃貸契約の解除、残置物の処理、敷金返還請求、遺産整理など多岐にわたる実務が一気に発生します。
厚生労働省のガイドラインは敷金の分別管理と速やかな返還を求めていますが、契約条項の理解不足がトラブルを招くのが現実です。
そこで、姫路市の行政書士が相続手続きをスムーズに進めるポイントを解説します。
サ高住の仕組みと契約の二重構造
サ高住とは
一般の賃貸住宅と同じ「賃貸借契約」を基盤としつつ、24時間スタッフによる安否確認・生活相談が付帯します。
介護サービスは外部の訪問介護事業所と個別に契約するため、介護保険の自己負担が生じます。
賃貸契約+生活支援サービス契約
入居時には敷金・保証金のほか、生活支援サービス契約を結びます。
国交省・厚労省「高齢者向け住宅ガイドライン」は、退去条件・原状回復費・敷金精算方法を重要事項説明書に明示するよう求めています。
契約解除の通知期限や残置物処理のルールは施設ごとに異なるため、家族も契約書を必ず共有しておきましょう。
身元保証人と連帯債務
多くのサ高住が身元保証人を求め、家賃・原状回復費・葬祭費まで連帯保証範囲に含めています。
家族で対応が難しい場合は保証会社や専門NPOを利用する選択肢も検討すると安心です。
入居者死亡後に必要な手続き
1 賃貸契約の解除と残置物処理
死亡届を提出したら速やかに施設へ連絡し、退去日と明け渡し期限を確定します。
ガイドラインでは「死亡後30日以内の明け渡し」が目安とされるため、行政書士が遺品整理業者や運送業者と連携し、残置物リストと写真を作成しておくとトラブル防止になります。
2 敷金・保証金の返還請求
原状回復費を差し引いた未使用額が相続人に返還されます。
請求には戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。
協議未了の場合は代表相続人が仮領収し、最終分割時に清算する方法もあります。
3 公共料金・外部サービスの名義変更/解約
電気・ガス・水道・通信・新聞などの契約は、死亡日で日割り精算し解約または名義変更を行います。
行政書士が一覧表を作成し、解約届や返金口座の指定書類を整備すると手間を削減できます。
相続手続きで求められる準備
財産目録の作成
サ高住入居者は自宅を売却済みのケースが多く、相続財産は預貯金・証券・保険が中心です。
通帳コピー・保険証券・証券会社IDを一覧化し、負債や保証債務も併記して家族で共有しましょう。
遺言書の有無を確認
公正証書遺言があれば検認不要で開示でき、相続手続きが数週間短縮されます。
自筆証書遺言なら家庭裁判所で検認を受けてから相続手続きに反映させます。
相続放棄・限定承認の検討
家賃滞納や医療費債務が残っている場合、資産と負債を比較し、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ放棄・限定承認を申述する必要があります。
行政書士が提供する支援とメリット
- 相続人確定・戸籍調査:出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を一覧化。
- 財産調査・目録作成:銀行照会状、保険会社請求書、不動産・証券調査を代行。
- 遺産分割協議書作成:相続人全員の合意を文書化し、敷金返還や家財売却益を盛り込む。
- 契約解約書類の整備:サ高住・公共料金・医療機関の解約届を一括で準備。
- 遺言書・エンディングノート支援:生前対策として公正証書遺言やACP(人生会議)の記録方法を提案。
まとめ ― サ高住入居は相続準備を始める絶好の機会
サ高住は自由度の高い住まいですが、賃貸借契約に基づく手続きが死亡と同時に発生します。
- 契約条項を家族と共有し、退去条件と敷金精算方法を把握する
- 財産目録と公正証書遺言を早期に整備する
- 行政書士と連携し、解約・相続・遺言をワンストップで管理する
これらを実践すれば、家族の負担を最小限に抑え、円満な相続を実現できます。
姫路市の行政書士に相談するには
当事務所ではサ高住関連の契約チェック、戸籍調査、財産目録作成、遺言・家族信託・成年後見導入支援、相続手続きを一括サポートしています。初回相談は無料です。
サ高住と相続でお困りの方は下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、個別案件は行政書士または専門家へ直接ご相談ください。
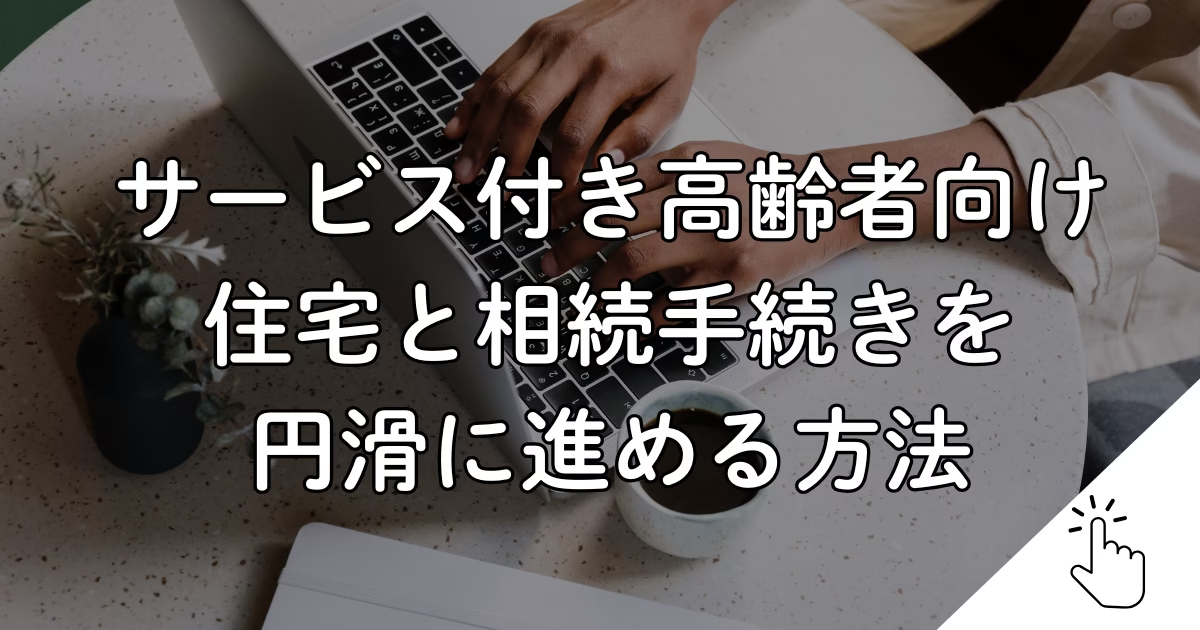
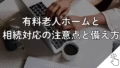
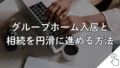
コメント