なぜ今、高齢者の引っ越しが増えているのか
「自宅の階段が負担になった」「病院やスーパーが遠い」「子どもと同居して安心したい」――こうした声を背景に、高齢者の住み替えニーズは年々高まっています。
国土交通省の住宅ストック統計では、65歳以上の単身世帯が2020年比で約1.3倍に増える見込みとされ、自宅のバリアフリー化や施設入居、子世帯との同居を検討する人が急増しています。
住まいの見直しは介護負担や相続、空き家問題まで波及するため、終活の一環として計画的に進めることが欠かせません。
高齢者が住み替えを決断する主な理由
身体機能の変化に合わせた住環境の再設計
年齢とともに脚力や視力は低下し、段差や階段、浴室のまたぎ動作が転倒リスクを生みます。
厚生労働省の高齢者事故統計では、家庭内転倒の4割が段差と浴室で発生しています。
築古の戸建てなどでは、段差が多くあったり、断熱が不十分でヒートショックの危険が高かったりします。
バリアフリー住宅やエレベーター付きマンションへの移転は、将来の介護負担を軽減する現実的な選択肢になります。
家族・介護との距離を縮める安心感
離れて暮らす子ども世帯の近くに引っ越すことで、見守りと緊急時のサポートが得やすくなります。
介護保険法13条の「住所地特例」を活用すれば、市外の介護施設へ転居しても介護保険料は転出元自治体で継続計算されるため、経済的負担が急増しません。
財産管理と空き家リスクの回避
築年数の古い戸建てを残したまま施設に移ると、固定資産税や維持管理が家族の負担になります。
空き家対策特別措置法14条は倒壊危険のある「特定空家」に行政代執行を命じ、固定資産税を最大6倍にする可能性を示しています。
住み替えと同時に売却や賃貸、解体を検討し、相続時のトラブルを未然に防ぐことが重要です。
住み替えを成功させるステップ
① 引っ越し先の候補を複数比較する
交通機関の利便性、近隣医療機関、買い物環境、バリアフリー仕様の程度をチェックし、可能なら平日と休日の両方で下見します。
サービス付き高齢者向け住宅の場合、安否確認や生活相談サービスの内容が施設ごとに異なるため、契約前にパンフレットと重要事項説明書を照合してください。
② 不動産の売却・賃貸手続きを整理する
自宅を売却するなら、宅地建物取引業法34条の2に基づく媒介契約書面(専属専任・専任・一般の3区分)を締結し、クーリングオフ(8日間)を活用して慎重に検討します。
賃貸へ回す場合は、入居者募集と管理委託契約をセットで依頼し、将来の修繕費を家賃収入で賄えるか試算しましょう。
③ 賃貸住宅から施設入居へ転居する際の退去精算
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担とされています。
退去時に高額請求された場合はガイドラインを提示し、写真や見積書で交渉の根拠を示すと合意が得やすくなります。
④ 引っ越し業者とスケジュールを早めに確定
高齢者向けの引っ越し支援会社は荷造り・不用品処分を一括で請け負い、介護ベッドの搬出にも対応しています。
繁忙期(3月・9月)を避け、余裕を持った見積もり依頼が費用節減につながります。
⑤ 公的手続きと契約変更を同時進行
住民票やマイナンバーカード、介護保険資格、年金の住所変更は市区町村窓口と年金事務所で行います。
日本郵便の死亡・転居届を提出すれば郵便物が継続転送され、個人情報流出リスクを抑えられます。
公共料金・新聞・インターネットの解約や移転を一覧表で管理すると漏れを防げます。
行政書士が支援できるポイント
財産整理と相続対策をワンストップで連携
住み替えは不要不動産や預貯金を一覧化する好機です。
行政書士は財産目録の作成を支援し、遺言書や家族信託で資産承継ルートを明示します。
これにより、空き家問題や相続税対策を先行的に解決できます。
契約書類のチェックと名義変更サポート
不動産売買契約書、施設入居契約書、管理委託契約書などを法的観点から確認し、見落としを防ぎます。
登記名義変更は司法書士、媒介報酬交渉は宅建士と連携して進めるため、手続きが一本化されます。
エンディングノートで家族と情報共有
新居の住所、主治医、介護方針、連絡先リストをエンディングノートに書き込み、家族と共有することで、いざという時の連絡漏れや医療・介護の意思決定をスムーズにします。
雛型や記入アドバイスは行政書士が提供します。
姫路市での住み替え支援事例
築50年戸建て売却と施設入居を同時進行
80代女性が要支援2となり、バリアフリー施設へ移る事例では、媒介契約書面を精査しました。
市の「住生活総合支援補助金」を活用して解体費の一部を賄い、売却益は入居一時金に充当する計画を立てました。
子世帯同居に伴う住所地特例の申請
父親が市外で介護付きマンションへ入居する際、介護保険住所地特例の届出書を行政書士が代理作成し、転出前自治体の保険料区分が継続されたため、費用負担が想定より軽く済みました。
住み替えは未来の安心をつくる前向きな準備
高齢者の引っ越しは暮らしの再設計であり、終活の重要なステップです。
バリアフリーや家族との距離、財産管理を総合的に考え、自分らしい住まいを選ぶことがこれからの安心につながります。
ただ注意しなければいけないのは、もう少し生活に支障がでるようになってから追々考えようという見方です。
いざ歩行困難になってきた、認知症の気がしてきたなどの症状がでてから、自宅を引き払って引っ越しなどはまず無理です。
これまでの経験から終の棲家としての引っ越しは、60代、遅くとも70代前半までにしておかなかれば、気力、体力ともに耐えることができないでしょう。
専門家と協力しながら、無理なく計画的に進めていきましょう。
行政書士への相談窓口(姫路市対応)
当行政書士事務所では高齢者住み替え診断、エンディングノート雛型の無料配布、不動産売却・施設契約書のチェック、相続対策まで一括支援しています。
初回相談は無料ですので、終活 住み替えや空き家売却でお悩みの方は、下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別案件は行政書士または関係専門家へ直接ご相談ください。
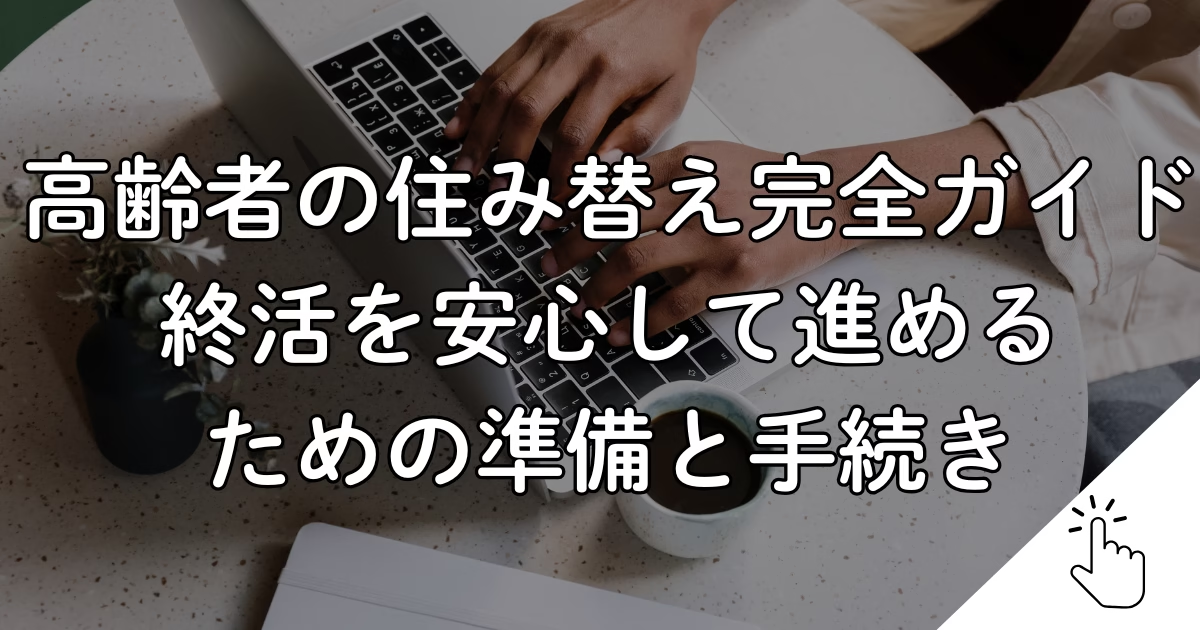
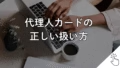
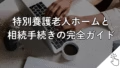
コメント