介護医療院と相続を同時に考える必要性
介護医療院は介護保険法8条の30で定義された、医療と介護を一体的に提供する長期療養型施設です。
医師・看護師が常駐し、終末期の緩和ケアにも対応できるため、人生の最終段階を過ごす場として利用が広がっています。
入所を機に「相続」や「遺言」を整えようとする相談が姫路市でも増えており、介護と相続を同時に設計することが家族の安心につながります。
介護医療院とは?その役割と特徴
介護医療院の位置づけ
介護老人保健施設や特養とは異なり、医療依存度が高い方を長期に支える施設サービス契約で、厚生労働省の運営指導指針に基づき預り金を分別管理する義務があります。
介護老人保健施設や特養については、別ブログ記事を参考にしてください。
入所要件と費用
要介護1以上で医療的ケアが必要な方が対象です。
介護保険が適用されますが、居住費・食費・日用品費など自己負担が発生します。
低所得者は市町村の負担限度額認定証を取得すれば軽減され、死亡月でも還付対象になります。
自宅不在による財産管理の課題
長期入所で自宅が空き家化すると、空き家対策特別措置法14条に基づき固定資産税が最大6倍になるリスクがあります。
預金や証券の管理も本人が行えなくなるため、事前に家族と連携して体制を整えることが不可欠です。
介護医療院入所を機に始める相続対策
財産目録の作成と保管
預貯金通帳、不動産登記簿謄本、保険証券、年金通知書を一覧化し、保管場所を家族と共有します。
厚労省の預り金ガイドラインによると、施設が預金を預かる場合は月次残高報告が義務付けられており、その写しを目録に綴じておくと後日の説明責任を果たしやすくなります。
遺言書の作成と公正証書化
体調が安定しているうちに公正証書遺言を作成すると、検認が不要で相続手続きが数週間短縮されます。
公証人は施設に出張できるため、移動が難しい入所者でも安心です。
成年後見制度と家族信託の検討
判断能力が低下した後は、家庭裁判所の選任した成年後見人が医療費や利用料を管理します。
自宅売却や資産運用を継続したい場合は、家族信託契約を締結し、受託者名義の信託口座から費用を支払う仕組みが有効です。
行政書士は後見申立書や信託契約書の作成を支援します。
相続発生時の具体的対応と施設との連携
施設への連絡と契約解消
死亡時は速やかに施設へ届出を行い、退所日を確定します。
運営指導指針では預り金返還を30日以内と定めており、未精算分は日割りで計算されます。
相続財産の整理と評価
高額医療費や生活費として出金が続いているため、通帳と領収書で支出根拠を確認します。
高額介護サービス費の還付金も相続財産に含まれるため、国税庁の財産評価基本通達を参照し、課税対象か判断します。
遺産分割協議と文書化
身元保証人が立替えた医療費・葬祭費を債権計上し、相続人全員で遺産分割協議を行います。
行政書士は協議書作成のほか、相続登記や預金払戻しに必要な戸籍収集も代行し、公平で円滑な相続を実現します。
行政書士が支援できる内容
財産目録・遺言書作成支援
財産確認・文案作成・公証役場との日程調整・証人手配までをワンストップで対応します。
成年後見・家族信託手続き
後見申立書、信託契約書、金融機関手続き書類を代行作成し、家族が安心して資産を管理できる体制を構築します。
相続発生後のトータルサポート
相続人調査、財産評価、協議書作成、登記・預金解約に必要な書類の整備まで一括支援し、専門家ネットワークで税理士・司法書士とも連携します。
まとめ:介護医療院入所を契機に相続準備を整える
介護医療院は終末期まで安心して過ごせる一方、長期入所が前提となるため、財産管理と相続準備を同時に進める必要があります。
- 財産目録と公正証書遺言を早期に整備
- 成年後見・家族信託で資産を安全に運用
- 死亡後は預り金返還・高額介護サービス費還付を漏らさず請求
行政書士と連携すれば、介護と相続を一括でマネジメントでき、家族の負担を大幅に減らせます。
行政書士への相談窓口(姫路市対応)
当事務所では介護医療院入所者とご家族を対象に、遺言書・家族信託・成年後見・相続手続きまで包括支援しています。
初回相談は無料です。介護医療院、相続や預り金精算でお悩みの方は下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、個別案件は行政書士または専門家へ直接ご相談ください。
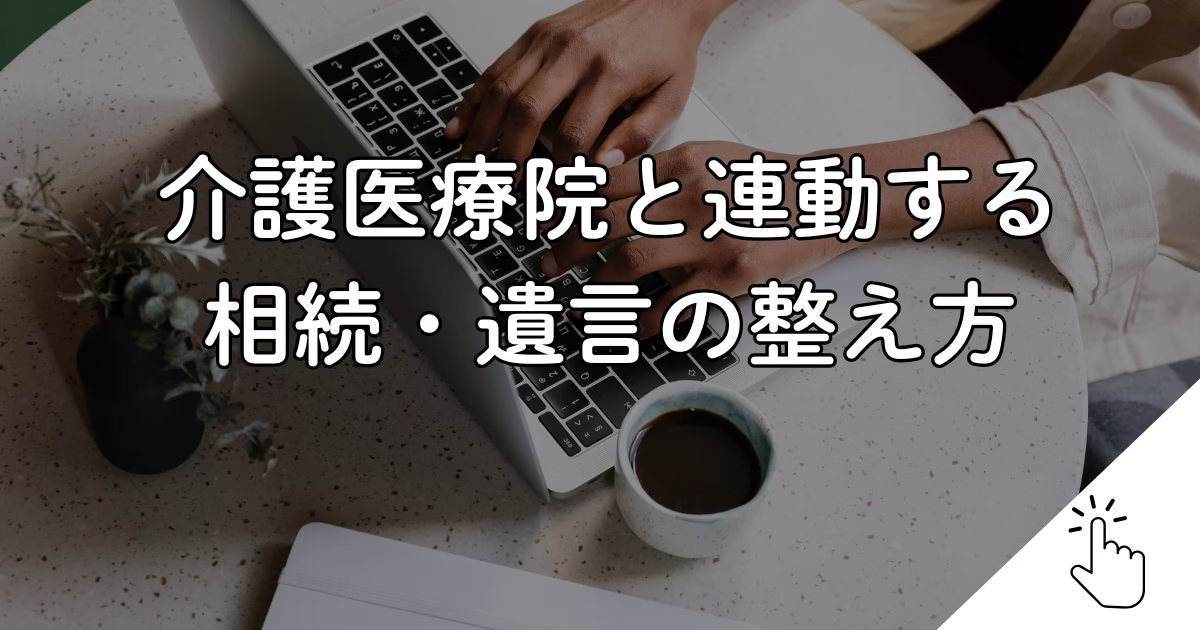
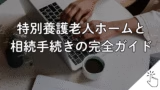
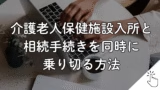
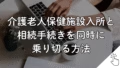
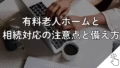
コメント