障害のある相続人を守る障害者控除とは
相続税が発生するとき、相続人の生活状況や健康状態は考慮されなければなりません。
特に障害のある相続人にとって、相続財産は将来の介護や医療費を支える重要な資金になります。
負担が過大にならないよう、相続税法十九条の四には「障害者控除」という税額控除が設けられています。
制度を正しく理解し申告書に反映すれば、相続税を大幅に軽減し、家族の経済的安心を確保できます。
障害者控除とは?制度の基本概要
障害者控除の対象者と適用要件
障害者控除は、相続開始日に二十歳以上八十五歳未満で、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など公的手帳により障害者と認定されている相続人が対象になります。
身分証明書や医師の診断書だけでは足りず、手帳等級で判定される点が特徴です。
制度の詳細は国税庁の「障害者控除のあらまし」で確認できます。
控除額の計算方法
控除額は八十五歳に達するまでの年数を基準に計算します。
一般障害者は残年数に十万円を掛け、特別障害者は二十万円を掛けます。
年数に一年未満の端数があるときは切り上げて一年として扱います。
たとえば、六十歳の特別障害者が相続人の場合、八十五歳まで残り二十五年なので、二十五年掛ける二十万円で五百万円が控除されます。
特別障害者と一般障害者の違い
身体障害者手帳一級または二級、精神障害者保健福祉手帳一級、重度知的障害と認定された人は特別障害者に該当します。
身体障害者手帳三級から六級など比較的軽度の等級は一般障害者に区分されます。
控除額は特別障害者のほうが倍額になるため、手帳の等級を正確に確認することが大切です。
行政書士が解説する障害者控除の実務と申告の流れ
控除を受けるために必要な書類
障害者控除を適用するには、相続税申告書第二表に控除額を記載し、障害者手帳の写しや戸籍謄本で年齢と等級を確認できるようにします。
税務署へ提出する際に手帳写しは必須書類ではありませんが、提示を求められたときに備え保管しておくと安心です。
行政書士は戸籍・住民票・法定相続情報一覧図を整え、税理士と連携して申告書を作成します。
申告書記載時の注意点
相続開始日と誕生日の前日を基準に年齢を判定するため、一日違いで控除額が変わる場合があります。控除額欄には等級ごとの計算結果を正確に転記し、未成年者控除など他の税額控除と併用するときは別欄で計算して合計額を差し引く必要があります。
他の控除制度との併用
障害者控除は基礎控除や配偶者の税額軽減、未成年者控除などと併用できます。
たとえば十八歳の特別障害者が相続人であれば、未成年者控除二十万円と障害者控除(特別障害者の場合)千三百四十万円を同時に適用して相続税を減額できます。
未成年者控除については、別ブログ記事にて詳しく解説しています。
障害者控除が適用される代表的なケース
身体障害者手帳二級の相続人
姫路市で父が亡くなり、五十歳の身体障害者手帳二級の長男が相続人となった事例では、長男が特別障害者と認定され、八十五歳まで三十五年分に当たる七百万円を相続税額から控除しました。
精神障害者保健福祉手帳一級を持つ相続人
母が亡くなり、精神障害者一級の65歳の娘が相続人となったケースでは、残年数二十年掛ける二十万円で四百万円の控除を適用し、納付税額を圧縮しました。
法定後見制度利用者が相続人になった場合
知的障害のある相続人が後見制度を利用している場合、後見人が申告を行います。
当行政書士事務所では後見人業務も行えますので、申告書を整えることで、控除漏れなく手続きを終えられました。
まとめと結論:障害者控除を確実に活用して負担を軽減する
障害者控除は、障害のある相続人を経済的に支える重要な制度です。
手帳等級と年齢を正しく確認し、相続税申告書に記載すれば、数百万円規模の税額軽減が期待できます。
申告期限内に漏れなく記入するには、行政書士や税理士など専門家の助力が有効です。
行政書士に相談するメリットとお問い合わせ情報(姫路市エリア対応)
当行政書士事務所では戸籍収集、手帳等級確認、法定相続情報一覧図作成、財産目録整備を通じて障害者控除の適用をサポートします。
障害のある家族が相続人になる場合は、下の問い合わせページから早めに相談し、安心して相続手続きを進めましょう。
※本記事は令和六年四月一日現在の相続税法および国税庁タックスアンサー№4156を参照して執筆しました。法改正や通達改訂が行われる可能性がありますので、最新情報は国税庁や財務省の公式サイトをご確認ください。
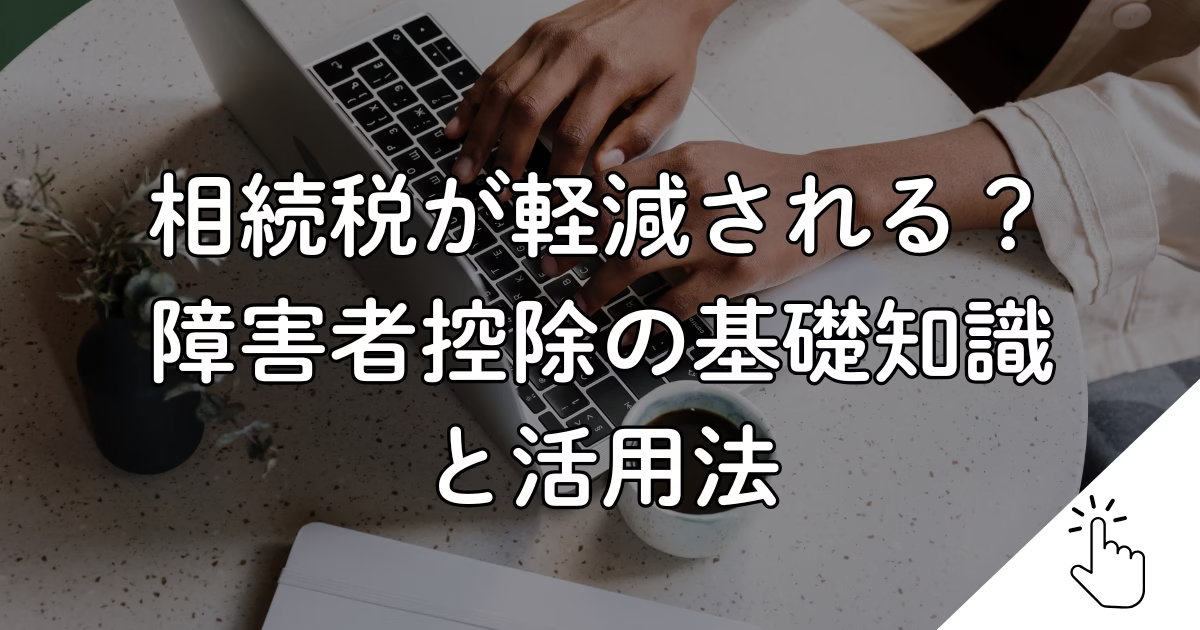
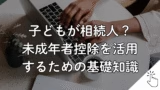
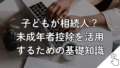
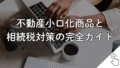
コメント