はじめに:相続対策に“組み合わせの発想”を
相続対策というと、「贈与」や「家族信託」がまず思い浮かぶ方が多いかもしれません。 いずれも有効な方法ですが、どちらか一つに絞るだけでは、十分な対策ができないこともあります。
そこで注目されているのが、資産管理法人を“組み合わせの軸”に使う設計です。 本記事では、兵庫県姫路市の行政書士の視点から、資産管理法人・贈与・家族信託の違いや、それぞれの強みと限界、そして併用することで生まれる新しい可能性についてわかりやすく解説します。
贈与とは?|手軽さが魅力、でも節税は限定的
贈与は、財産を無償で他人に移転する制度で、相続対策の第一歩としてよく使われます。たとえば、毎年110万円以内の非課税枠を使う「暦年贈与」は非常に有名です。
✅ メリット
- 手続きが比較的簡単(契約書+名義変更程度)
- 名義がすぐに変わるため、財産の分散が進む
- 贈与した財産は原則として相続財産に含まれない(例外あり)
⚠ デメリット
- 110万円を超えると贈与税が高率(最大55%)
- 財産評価額は原則そのまま(時価)で課税される
- 生前贈与加算のルールに注意が必要(相続前7年以内など)
📌 国税庁「贈与税の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
家族信託とは?|柔軟な財産管理と認知症対策に強み
家族信託は、「家族の誰かに財産の管理・運用を任せる」制度です。生前に設計することで、認知症や意思判断能力の低下に備える方法として注目されています。
✅ メリット
- 認知症対策として非常に有効(成年後見より柔軟)
- 財産の管理権限と受益権を分けられる
- 遺言に近い機能や、死後の使途指定も可能
⚠ デメリット
- 契約書の作成、登記、信託口口座の開設など複雑な手続きが必要
- 税務・法務の知識がなければ難しい
- 不動産の信託は登録免許税が課税される場合もある
資産管理法人とは?|承継の器としての価値
資産管理法人とは、個人が所有していた資産(主に不動産や株式など)を法人名義に切り替え、法人として所有・管理・運用する仕組みです。
ここで注目したいのは、相続時に「不動産を分ける」必要がなくなり、「法人株式の分割」で対応できるという点です。
✅ メリット
- 不動産を株式という形に変換できるため、分割がスムーズ
- 株式評価方法により、相続税評価額を圧縮できる余地あり
- 経営を通じた次世代教育や事業承継に有効
⚠ デメリット
- 法人の維持費(登記・決算・会計処理など)がかかる
- 法的・税務的な仕組みをしっかり理解する必要あり
3者の違いを比較する
| 比較項目 | 贈与 | 家族信託 | 資産管理法人 |
|---|---|---|---|
| 節税効果 | 限定的 | ケースにより高い | 工夫次第で高い(評価圧縮) |
| 分割性 | 高い(名義ごと分ける) | 柔軟に設計可能 | 株式分割で調整可能 |
| 認知症対策 | ✕ | ◎ | △(法人単体では不可) |
| 実務の柔軟性 | ◯ | ◎ | ◯ |
| 手間・コスト | 低 | 中〜高 | 中〜高 |
| 専門性の必要 | 低 | 高 | 高 |
併用がベストな理由|“単独では足りない”を補完する
📌 なぜ併用設計が有効なのか?
相続には、「誰にどの財産を」「どのタイミングで」「どう使ってもらいたいか」といった多面的な設計が求められます。
たとえば:
- 家族信託で“判断能力の低下”に備え、運用を将来財産を承継する家族が管理
- 法人で“資産の集約”と“相続時の分割対策”を構築
- 贈与で“少額資産を生前に移転”して節税しながら承継意識を育てる
📍 組み合わせ例
| 対策対象 | 活用方法 |
| 高額不動産 | 法人名義で集約し、株式で承継 |
| 預金や小口資産 | 暦年贈与で分散移転 |
| 認知症・介護期 | 家族信託で財産管理体制を構築 |
まとめ:相続対策は“選ぶ”のではなく“組み立てる”もの
贈与・家族信託・資産管理法人のいずれもが、相続対策として有効です。 しかし、どれか一つに頼るのではなく、それぞれの特性を活かして組み合わせることで、より効果的で柔軟な対策が可能になります。
✅ 贈与で「早めの承継」
✅ 家族信託で「判断能力の喪失リスク」対策
✅ 法人で「長期的な資産の整理・分割・承継」を支える
こうした設計は、一人で考えるには複雑です。 相続は一度きりだからこそ、専門家とともに“ご家族ごとに最適な組み合わせ”を構築することが大切です。
ご相談はこちら|組み合わせ戦略はプロにお任せ
兵庫県姫路市で相続対策をご検討の方へ。行政書士として、家族信託契約書の作成、法人設立サポート、贈与計画の立案まで一貫したサポートを行っております。
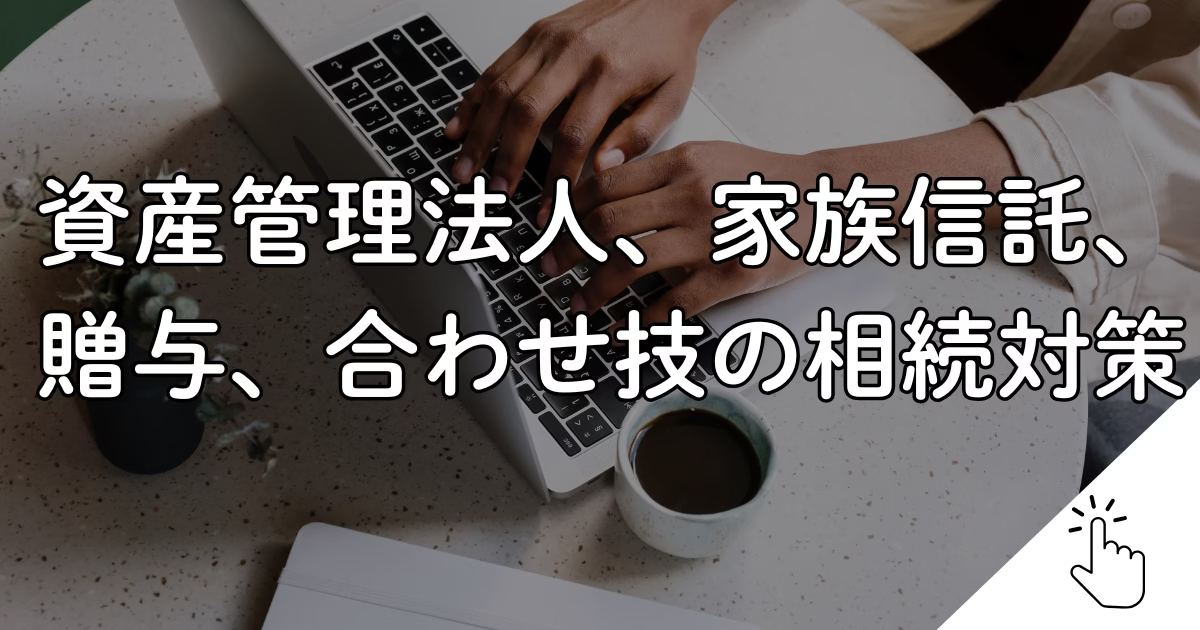
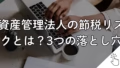
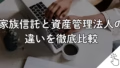
コメント