在宅介護の増加と相続準備の重要性
介護保険法に基づく在宅サービスの中でも、訪問介護(ホームヘルプ)は「住み慣れた自宅で最期まで暮らしたい」という高齢者の希望を支える要です。
厚生労働省統計によれば、要介護認定者の約六割が訪問介護を利用しており、今後も利用者は増加すると見込まれます。
しかし利用者が亡くなると、サービス契約の終了手続きや費用清算、財産管理をめぐり相続人間でトラブルが起こることが少なくありません。
ここでは行政書士の視点から、訪問介護利用者の相続を円滑に進める準備と手続きのポイントを解説します。
訪問介護の仕組みと契約内容
訪問介護とは
介護保険法八条二項に位置づけられる訪問介護は、要支援または要介護と認定された本人の居宅をヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスです。
サービス回数や内容はケアマネジャーが作成する居宅サービス計画に基づき、介護給付費は九割または七割を公費で賄う仕組みです。
利用契約と家族の役割
サービス契約は原則として本人と事業者で締結しますが、本人の判断能力や体調によっては家族が署名や費用支払いを代行することがあります。
介護保険の給付対象外となる買い物代行や庭掃除などを「自費サービス」として契約するケースもあり、家族が契約内容を把握していないと死後の精算で混乱が生じやすくなります。
契約書、重要事項説明書、利用明細は日頃から家族や信頼できる第三者と共有しましょう。
相続発生時に必要な対応
サービス終了と費用精算
被相続人が亡くなったら、速やかに事業者へ連絡しサービス提供を停止します。
厚労省の契約マニュアルでは当月分利用料を日割り精算し、前払い金は全額返還することが望ましいと示されています。
未払い分がある場合は相続人が負担し、過誤請求で給付費を返還する場合は相続財産から充当されます。
返還金や追加請求の有無
契約形態によってはデポジットを預けていることがあります。
返還には戸籍謄本や遺産分割協議書の提出が必要になりがちです。
行政書士は必要書類を整え、返還金が相続財産として適切に計上されるようサポートします。
ケアマネジャーとの情報共有
ケアマネジャーは介護記録、生活状況、費用負担を把握しています。
死亡時に介護記録を入手しておくと、介護費用の立替額や在宅介護の実態を相続人同士で共有でき、寄与分の判断や高額介護サービス費還付の申請資料として役立ちます。
相続準備で欠かせない三つのステップ
財産棚卸しと目録作成
在宅で暮らす高齢者は生活費を預貯金から支出していることが多く、現金・年金・保険が中心財産になりやすい傾向があります。
通帳コピー、保険証券、年金通知書をまとめ、借入金や介護用リフォームローンの残高も記載した財産目録を作成し家族と共有すると、相続時の調査が短縮されます。
公正証書遺言で意思を可視化
意思能力が十分なうちに公正証書遺言を作成すれば、家庭裁判所での検認が不要になり、預金解約や不動産名義変更が数週間早く進みます。
ヘルパーや介護を担った家族への感謝を形にする「介護分の特別寄与料」を遺言に記載することも可能です。
家族信託・成年後見制度の活用
認知症進行が想定される場合は、家族信託で子を受託者に指名し、信託口座から介護費を払い出す方法が有効です。
判断能力が既に低下している場合は家庭裁判所に成年後見申立てを行い、後見人が契約管理や医療同意を担当します。
行政書士が提供できる支援
相続人調査と戸籍収集
出生から死亡までの戸籍を取得し、相続関係説明図を作成します。
音信不通の相続人がいる場合も、役所や郵便照会を活用して所在調査を行います。
財産調査と遺産分割協議書作成
銀行照会状、保険金請求書、固定資産税課税明細を取り寄せ、財産評価を確定します。
その上で相続人全員の合意を協議書にまとめ、公証役場で確定日付を付し紛争を予防します。
遺言・信託の設計と公証サポート
依頼者の意思を聴取し、遺言条項や信託条項を案文化します。
公証人との日程調整や証人手配を行い、法的に確実な生前対策を実現します。
姫路市での事例紹介
公正証書遺言で介護者へ配慮したケース
訪問介護を受ける八十代女性が行政書士とともに遺言を作成し、介護を担った長女へ特別寄与料を明示しました。死後は他の相続人も内容に納得し、二週間で預金解約と名義変更が完了しました。
遺言書を残さず、遺産分割協議で特別寄与料を主張しても、当人からすると”雀の涙”程度の金額しか認められない場合もあります。
事前に遺言書で面倒を見てくれた人に対しての感謝と、他の相続人への理解を求める文面を残しておくことが大切です。
まとめ:訪問介護と相続は早めの準備がカギ
一 在宅介護の契約書・利用明細を家族と共有
二 財産目録と公正証書遺言で相続の方向性を明確化
三 家族信託や成年後見で認知症・判断能力低下に備える
行政書士の伴走支援を活用すれば、介護契約の終了から遺産分割協議書作成まで一括で対応でき、相続トラブルを未然に防げます。
行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報(姫路市対応)
姫路市の行政書士事務所では、訪問介護利用者とご家族を対象に、戸籍調査、財産目録作成、遺言・家族信託・成年後見導入支援、遺産分割協議書作成をトータルサポートします。
初回相談は無料ですので、訪問介護と相続でお悩みの方は下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、個別の案件は行政書士または専門家へ直接ご相談ください。
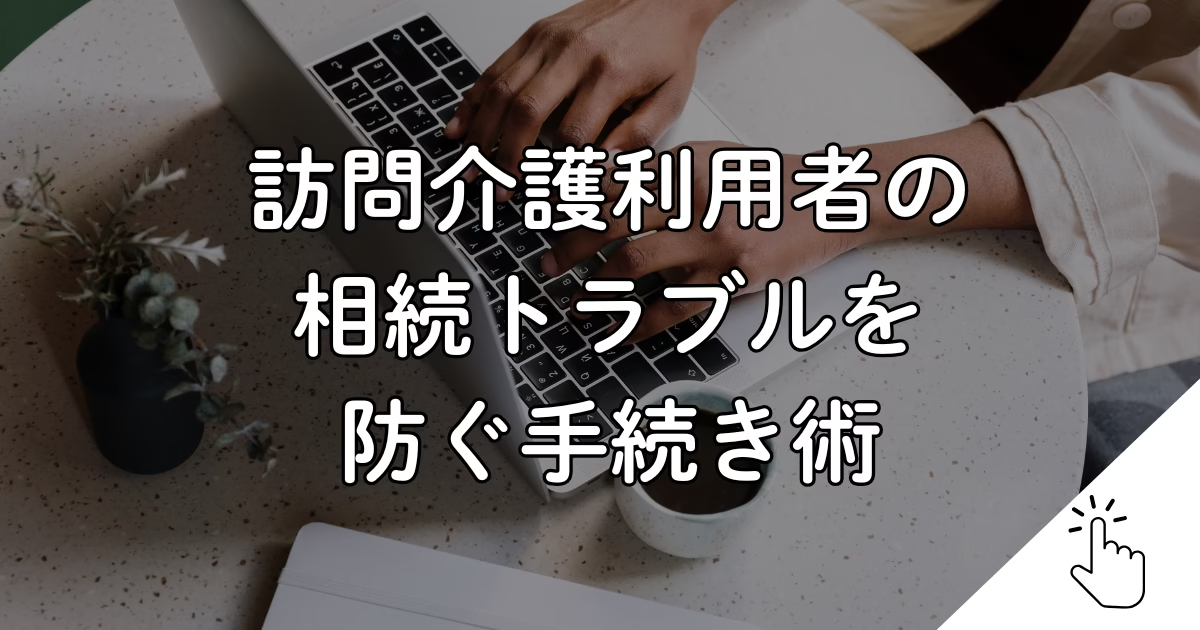
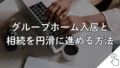
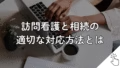
コメント