認知症高齢者が暮らすグループホームと相続問題
認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら支援を受けられるグループホームは、介護保険法八条十九で定義され、老人福祉法二十条の三に基づく届出が義務づけられています。
安心した住まいである一方、入居者が亡くなると契約解除や費用精算、保証金返還、残置物処理、相続手続きが短期間に集中します。
とくに認知症による意思能力低下があった場合には、成年後見や遺言の有効性確認など法的対応が複雑になりがちです。
この記事では、行政書士の視点から相続をスムーズに進めるポイントをまとめます。
グループホームの基本と契約内容の確認
グループホームとは
グループホームは認知症高齢者が五〜九人で暮らし、専門スタッフが二十四時間常駐して日常生活を支援します。
対象は要支援二以上で、家庭的な環境で自立を促すことが目的です。
利用契約の特徴と注意点
入居時、利用契約書で利用料・食費・管理費・保証金などを取り決めます。
厚生労働省の運営指針では、預り金を別口座で管理し、死亡後三十日以内に精算するよう求めています。
また身元保証人を設定する場合、連帯保証の範囲(利用料・医療費・原状回復費・遺体搬送費など)を必ず確認しましょう。
入居者が亡くなった際に必要な対応
施設への連絡と契約解除手続き
死亡が確認できたら速やかに施設へ報告し、死亡届提出や退去日を決定します。
運営指針は「死亡後三十日以内の退去」を目安にしており、残置物の搬出準備を急ぐ必要があります。
費用の清算と残置物の整理
月額利用料や日用品費の未払い分は日割りで精算し、原状回復費が差し引かれることがあります。
行政書士は領収書や写真付きの残置物リストを作成し、費用負担の根拠を施設と共有します。
保証金や返還金の取り扱い
保証金や未償却一時金がある場合、戸籍謄本や遺産分割協議書を添付して請求します。
返還金は相続財産として扱い、入金日と金額を財産目録に記録しておくと相続税申告が円滑です。
相続手続きで押さえる実務ポイント
財産目録の作成と相続人の確定
自宅を売却して現金化しているケースが多く、相続財産は金融資産中心です。
行政書士は出生から死亡までの戸籍を収集し、銀行・証券会社・保険会社へ残高照会を行い、正確な財産目録を作成します。
遺言書の有無と対応
公正証書遺言があれば検認不要で速やかに内容を実行できます。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受けてから手続きを進めます。
遺言書がなければ相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
認知症リスクへの備え
認知症によって意思能力が欠ける状態で作成された契約や遺言は無効となる可能性があります。
判断能力が低下する前に公正証書遺言や家族信託を整備し、判断能力低下後は成年後見人を選任しておくと安心です。
また認知機能しっかりしているうちに、信頼できる人を指名しておく任意後見も効果的です。
行政書士が提供する主な支援
相続人調査・戸籍収集
出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。
財産調査と遺産分割協議書作成
金融機関照会・保険請求を代行し、相続財産を確定。相続人間の合意内容を協議書にまとめます。
成年後見申立て・遺言作成支援
認知症進行時には後見申立書を作成し、後見人の就任をサポート。
生前の段階では公証役場と連携し公正証書遺言を整えます.
姫路市での実例
後見制度を活用し円満相続
後見人管理の帳簿があったため、死亡後の財産内容が明確で遺産分割がスムーズに完了。
公正証書遺言でトラブル回避
入居前に遺言を整備していた事例では、保証金返還と銀行解約が二週間で完了し、相続人同士の争いは起きませんでした。
まとめ:グループホーム入居を相続準備の契機に
- 契約条項(退去期限・保証金精算)を家族で共有する
- 財産目録と公正証書遺言を早めに整備する
- 成年後見や家族信託で判断能力低下に備える
行政書士に依頼すれば、契約解除から遺産分割協議書作成までワンストップで支援を受けられ、遺族の負担を大幅に軽減できます。
行政書士への相談方法(姫路市対応)
姫路市の行政書士事務所では、グループホームに関連する契約チェック、戸籍・財産調査、遺言・家族信託・成年後見導入、相続手続きを一括支援します。初回相談は無料ですので、下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、具体的な案件は行政書士または関係専門家へ直接ご相談ください。
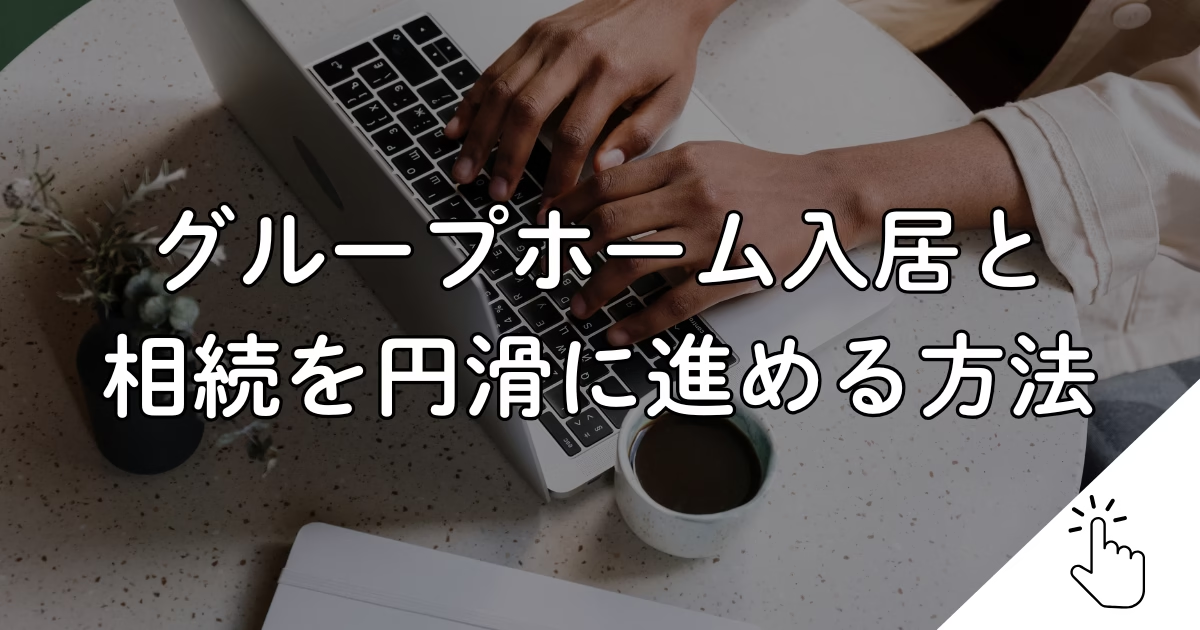
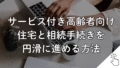
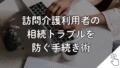
コメント