在宅支援サービスが相続実務に与える影響
介護保険法(第8条7項)に位置づけられる通所介護(デイサービス)は、食事・入浴・機能訓練などを日帰りで受けられる在宅支援の要です。
要支援・要介護高齢者の生活機能維持と介護者の負担軽減を同時に実現できる一方、利用者が亡くなった瞬間からサービス契約の終了、利用料の精算、医療費控除、高額介護サービス費還付、遺産分割協議など相続実務が一気に動き出します。
家族が慌てず対処できるよう、行政書士が押さえるべき連携ポイントを解説します。
通所介護の仕組みと契約内容を確認しよう
通所介護の役割
- 自立支援:理学療法士等による個別機能訓練や認知症予防プログラム
- 家族支援:ショートステイではなく日帰りで介護負担を軽減
- 社会参加:レクリエーションや地域交流で孤立を防止
契約内容と費用負担
契約は利用者(又は代理人)と事業者の間で締結し、重要事項説明書に訪問送迎・加算項目・キャンセル料が明記されます。
利用料の1〜3割は自己負担、残りは介護給付費です。
死亡月の利用料は日割り精算となり、過誤申立てで給付費返還が発生するケースもあるため、契約条項を家族で共有しておきましょう。
相続が発生したときの実務フロー
1 | サービス終了と利用料の清算
- 事業所へ死亡連絡
- 利用最終日の確定とキャンセル分の調整
- 未払い・前払い費用の精算(前払いは原則全額返還)
2 | 領収書・利用明細の保全
- 医療費控除:入浴介助加算・個別機能訓練加算は控除対象
- 高額介護サービス費:自己負担上限を超えた分は市区町村へ還付申請
- 還付決定通知書は相続財産に含めて財産目録へ計上
3 | 介護記録の取得と寄与分の証明
事業所は介護記録を2年間保存する義務があります。
家族がコピーを受領し、在宅介護の実態や家族の介護貢献度を可視化しておくと、遺産分割協議で特別寄与料を主張する根拠になります。
相続手続きを円滑にする3つの備え
① 財産目録と相続人確定
- 通帳コピー・保険証券・固定資産税通知書を整理
- 行政書士が出生から死亡までの戸籍を収集し相続関係説明図を作成
② 公正証書遺言で意思を明文化
- 家族に残すメッセージやデイサービス職員への感謝も遺贈事項に記載可能
- 公証役場で作成すれば検認不要で預金解約が迅速に
③ 家族信託と任意後見の組み合わせ
- 家族信託で「受託者=長男」が信託口座から利用料を支払い
- 判断能力低下後は任意後見人が医療・介護契約の代行
行政書士が提供するサポート
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 相続人調査 | 戸籍取得・相続関係説明図の作成 |
| 財産調査 | 銀行照会状・保険請求・不動産評価 |
| 遺産分割協議書 | 下書き→相続人合意→署名押印の進行管理 |
| 生前対策 | 公正証書遺言・家族信託契約・任意後見契約 |
まとめ|介護と相続の連携こそ家族を守るカギ
- 契約書と利用明細を共有し、死亡時の精算ルールを把握
- 財産目録と公正証書遺言を早期整備して手続きを短縮
- 行政書士の伴走支援で戸籍収集から遺産分割協議書作成までワンストップ対応
これらを実践すれば、デイサービス終了と相続手続きがスムーズにつながり、家族は看取りとグリーフケアに専念できます。
行政書士へのご相談窓口(姫路市対応)
姫路市の当行政書士事務所では、通所介護利用者とご家族向けに
- 相続人調査
- 財産目録作成
- 公正証書遺言・家族信託設計
- 遺産分割協議書の作成
- 医療費控除・高額介護サービス費申請サポート
を一括提供しています。初回相談は無料ですので、下の問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、個別の案件は行政書士または関係専門家へ直接ご相談ください。
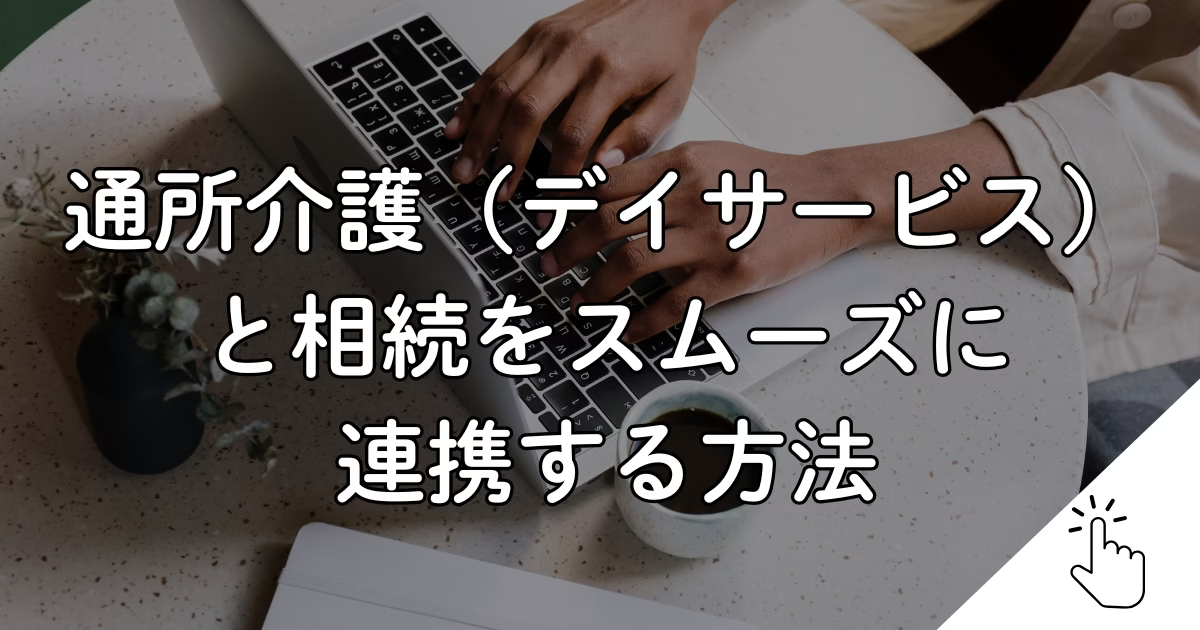
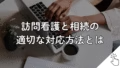

コメント