高齢化社会で注目が集まる代理人カードと相続の関係
銀行の「代理人カード」または「家族カード」は、高齢の親に代わって子が預金を引き出し、生活費や医療費を支払える便利な仕組みです。
姫路市でも介護負担の増加に伴い利用が広がりますが、名義人が亡くなった直後にトラブルへ発展する事例が後を絶ちません。
金融機関の普通預金規定では死亡届出時点で代理人カードは失効すると明示されており、三井住友銀行は第二十条で払い戻し停止を定めています。
つまり死亡後のカード利用は規約違反となり、相続人間の不信感や刑事・民事責任につながるおそれがあります。
ここでは行政書士の視点で、代理人カードを安全に運用し、相続で揉めないための実務ポイントを解説します。
代理人カードの仕組みと家庭内での役割
代理人カードは預金の「所有権」を移すものではなく、名義人の委任により第三者が入出金や残高照会を代行できるだけの権限を与えます。
名義人が体調を崩しても家族が介護施設費や医療費を即座に支払えるため、生活支援手段として機能します。
しかしカードを保有する家族が単独で管理すると、使途が不明確になりやすく、他の相続人に疑念を抱かせる温床となります。
名義預金との違いは、預金が誰の財産かが明確な点です。
名義預金は外見上の名義と実質的所有者が食い違うため、相続調査で税務署から追及されるリスクが高まります。
代理人カードの場合、預金はあくまでも名義人の相続財産に含まれ、相続開始と同時に口座は凍結されます。
相続発生後に起きやすい三つのトラブル
第一に、死亡後に代理人カードで引き出す行為が「遺産の不正な取り扱い」とみなされる点があります。
刑法二百五十二条は横領罪を規定しており、例え家族であったとしても不当な引き出しは刑事告発の対象にもなり得ますので、「お世話をしているのだから、報酬代わりにちょっと拝借しても大丈夫だろう」などとはお考えにならないようにしてください。
第二に、残高が合わない、出金理由が説明できないといった不透明な取引が相続人間の信頼を損ない、遺産分割協議を長期化させます。
第三に、金融機関の利用規定違反により返金請求や損害賠償に発展するケースも見受けられます。
なお、二〇二四年改正民法で創設された「預貯金の一部払戻し制度」(民法九百九条の二)を使えば、相続人は戸籍一式を添えて銀行に請求し、一人当たり百五十万円を上限に仮払いを受け取ることが可能です。
これにより、死亡後の生活費や葬儀費用を代理人カードなしでも賄えるため、無用な引き出しを避けられます。
代理人カードを安全に運用する三つのルール
最初に利用範囲を家族会議で決め、引き出し目的と限度額をメモに残します。
本人の意思確認を動画や書面で保存しておくと、後日に説明責任を果たしやすくなります。
次に出金履歴を定期的に共有し、取引明細をクラウドで相続人全員が確認できる仕組みを整えます。
領収書がでない出費については、出金伝票か適当な紙に、日付、用途をはっきり書いて保存しておきましょう。
最後に将来の相続トラブルを見据え、家族信託や公正証書遺言でカード利用の経緯と残高の帰属先を明示しておくと安心です。
受益者連続型家族信託を活用すれば、委託者死亡後も受託者が同口座を一貫して管理でき、凍結リスクを回避できます。
行政書士が提供できる相続時の支援
行政書士は銀行取引明細を整理し、代理人カードを介した入出金の目的を文章化する「事情説明書」を作成します。
これを遺産分割協議書に添付すれば、不信感が払拭され協議が円滑になります。
また生前対策として、カードの使用範囲を定めた委任契約書や遺言書の原案を作成し、家族で署名しておく方法も実務的です。
金融機関との具体交渉や訴訟対応は弁護士の分野になりますが、行政書士は書面作成と手続き案内で相続実務の土台を整えます。
まとめ―適切なカード管理が家族の未来を守る
代理人カードは高齢者の暮らしを支える便利な仕組みですが、死亡後に使えば規約違反となり、刑事・民事リスクを招きます。
生前に利用ルールを文書化し、定期的に取引を共有し、遺言や家族信託で権利関係を整理しておくことがトラブル予防の近道です。
行政書士や弁護士と連携し、安心して終活と相続を進めましょう。
行政書士への相談窓口(姫路市対応)
当行政書士事務所では代理人カードの記録整理、相続財産調査、遺言書・家族信託の作成支援を承っています。初回相談は無料ですので、下の問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
※本記事は一般的な法情報の提供を目的としており、個別案件は行政書士または専門家へ直接ご相談ください。
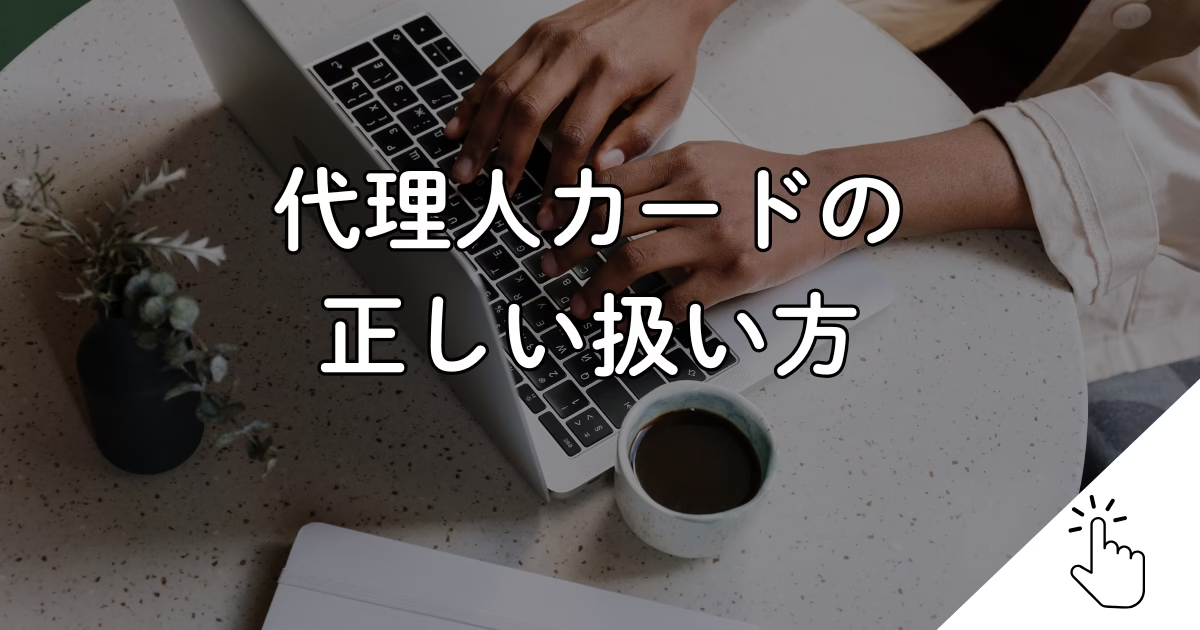
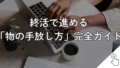
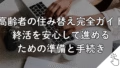
コメント