本記事は一般的な情報をお伝えするもので、個別の法的アドバイスには該当しません。具体的なご事情は専門家へご相談ください。
「親が亡くなったあと、通帳を使ってお金を引き出そうと思ったら、口座が凍結されていた」──そんな話を聞いたことはありませんか?実はこれ、多くのご家庭で起きている“相続の落とし穴”のひとつです。
私は行政書士として兵庫県姫路市で相続や遺言に関するご相談を日々受けていますが、「お金があるのに使えない」状態に陥ったご家族の困惑や不安に何度も立ち会ってきました。本記事では、銀行口座が凍結される理由とその影響、そして今すぐできる3つの対策について解説します。
口座が凍結される仕組みを理解する
銀行が行う凍結のフロー
人が亡くなると、その預貯金は相続財産となります。金融機関が死亡を把握した時点で、引き出しや振替は停止されます。死亡の情報は遺族の連絡だけでなく、市町村からの通知や新聞のお悔やみ欄などからも伝わります。こうした凍結は、不正引き出しと相続トラブルを防止する法令上の措置にあたります。一般社団法人 全国銀行協会
凍結解除に必要な書類と期間
凍結解除には、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本と印鑑証明書、そして金融機関指定の相続手続書類が必要です。全国銀行協会が示す標準書類一覧によれば、書類準備と審査に数週間から数か月かかる場合があります。一般社団法人 全国銀行協会
凍結が家計に与える3つの影響
- 葬儀費用や医療費を立て替える負担が生じる
- 生活費や当面の支払いが滞る恐れが高まる
- 遺産分割が長引けば、凍結解除まで1年以上を要することもある
これらの事態は、ご遺族の心労と金銭的ストレスを大きくします。
今すぐできる3つの備え
① 生前贈与と共有口座を計画的に活用する
年間110万円までの暦年贈与は贈与税が課税されません。国税庁の解説でも基礎控除の範囲内であれば申告不要と示されています。国税庁
ただし、無計画な共有口座は名義預金の疑いを招きます。贈与契約書を作成する、入出金を明確に記録するなど、後日の説明責任を見据えて準備します。
② 遺言書で口座の帰属と遺言執行者を指定する
公正証書遺言で口座ごとの承継者を明確にし、遺言執行者を指名しておくと、家庭裁判所の検認が不要となり、速やかに解凍手続きが進みます。相続人間で意見が割れやすい生活口座ほど明示しておくと安心です。
③ 民法909条の2「預貯金の仮払い制度」を理解しておく
2020年施行の改正で、遺産分割協議前でも各相続人は「法定相続分 × 1/3」かつ1金融機関あたり150万円までを単独請求できます。法務省の制度概要は、生活費や葬儀費用を確保する応急措置として紹介されています。法務省、一般社団法人 全国銀行協会
行政書士が支援できること
| サポート内容 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書作成支援 | ヒアリング→文案作成→公証役場調整 | |
| 相続関係説明図・戸籍収集 | 相続人を確定し書類を整理 | 書類不備による差し戻しを防止 |
| 金融機関提出書類の整備 | 相続届・払戻請求書の作成サポート | 各行の独自様式に合わせて作成 |
まとめ
銀行口座の凍結は、突然起きるうえに家計へ深刻な影響を及ぼします。遺言書による指定、生前贈与の活用、仮払い制度の理解といった備えを重ねることで、ご家族は安心して葬儀や相続手続きを進められます。
無料リスク診断と相談窓口
LINEで気軽に質問:ボタンひとつでチャット相談が可能です
まずは不安を共有し、専門家と一緒に対策を整理しましょう。初回相談は費用がかかりません。
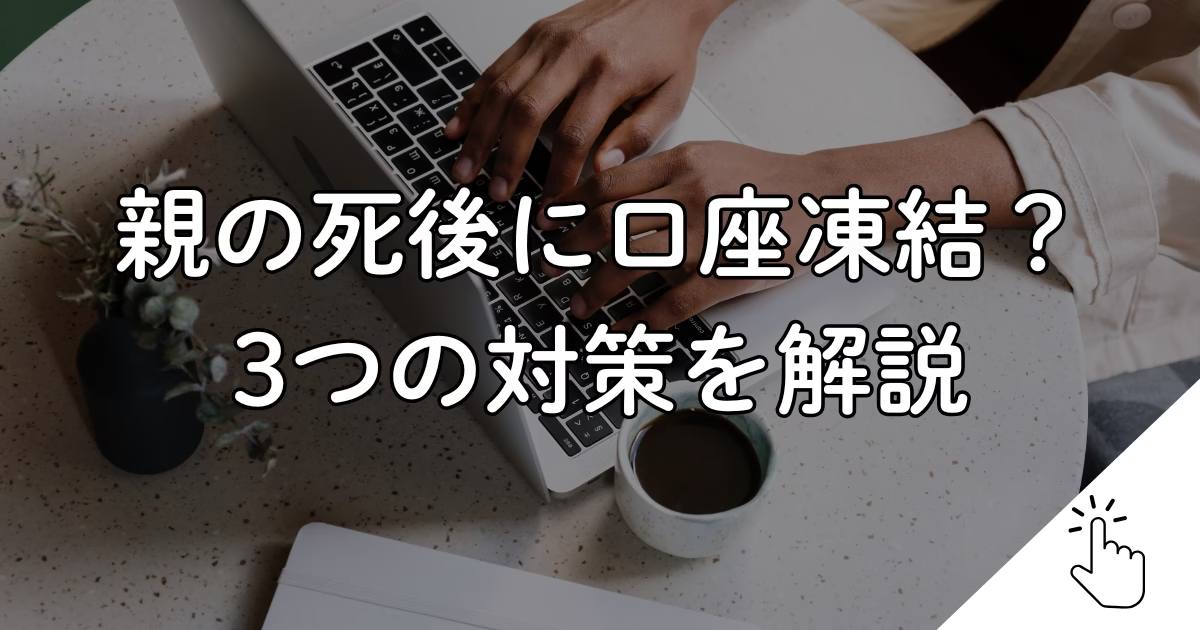
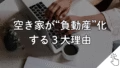
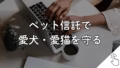
コメント